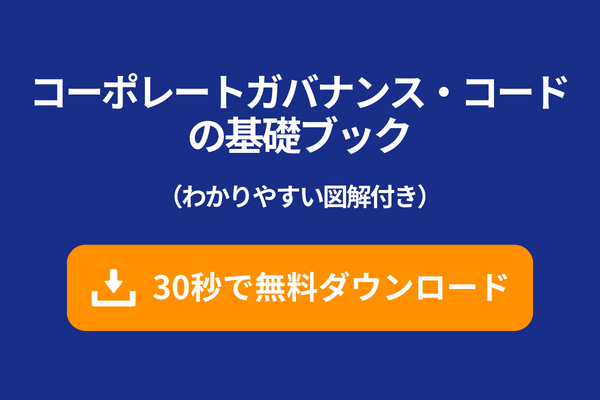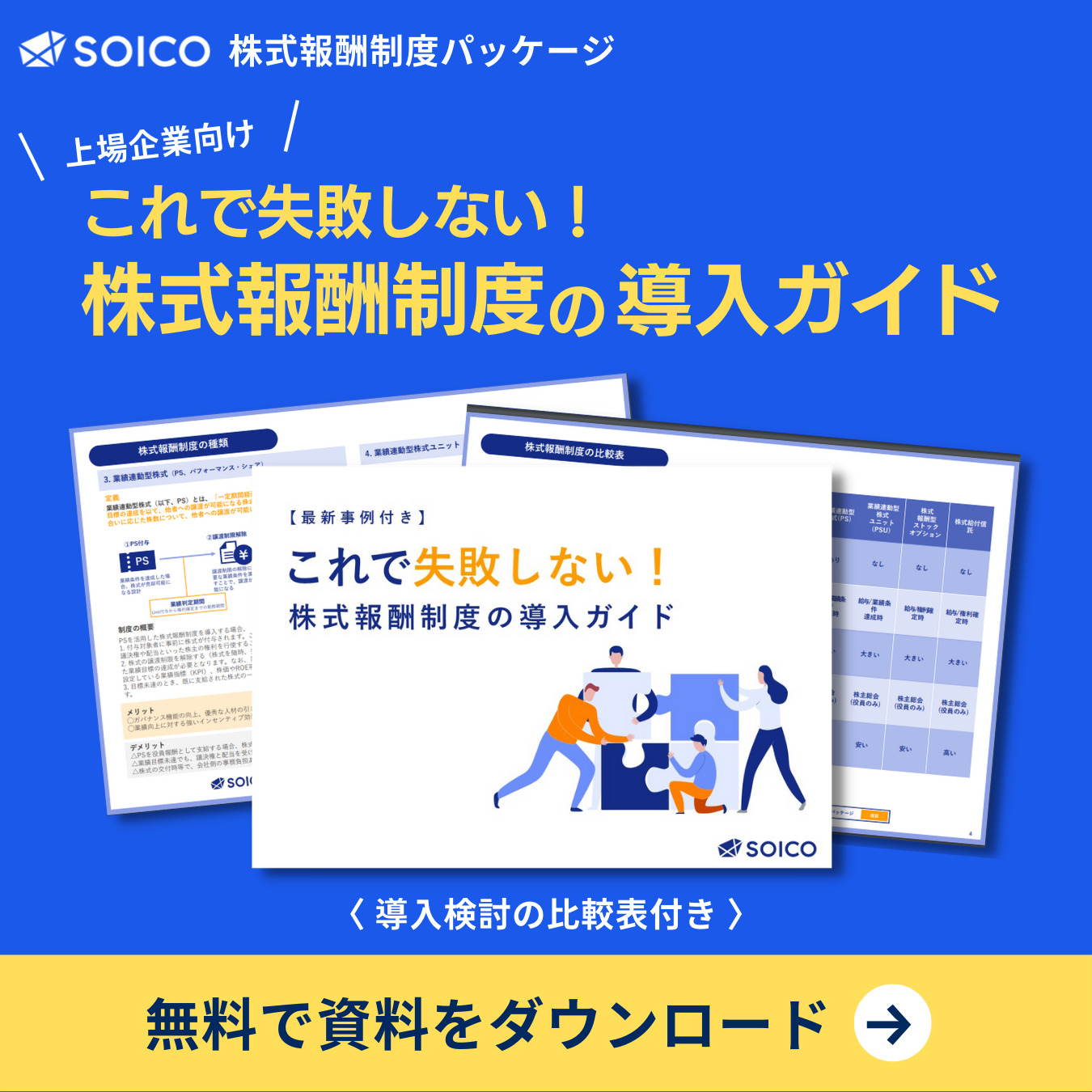COLUMN
コラム
コンプライ・オア・エクスプレイン|コンプライアンスへの対応・意義・必要性について解説
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)



コーポレートガバナンス・コードの基本のキ
~概要と基本原則を解説~
コーポレートガバナンス・コードの「基本的な概要」と「基本原則」にフォーカスして紹介
2015年にコーポレートガバナンス・コードが制定されましたが、その中で企業がステークホルダーの期待に応えて、企業の持続的な成長とステークホルダーにおける利益の確保を実現していくために、経営資源の配分を考えていくことが重要であるとしています。
その中で、企業とステークホルダーが建設的な対話を実現していくためにも、コーポレートガバナンス・コードでは、コンプライ・オア・エクスプレインを採用しております。
本記事では、コンプライ・オア・エクスプレインの考え方や必要性・意義、対象範囲、また具体的な内容についてご紹介します。
目次
コンプライ・オア・エクスプレインとは

コンプライ・オア・エクスプレインとは、コーポレートガバナンス・コードにおいて原則を遵守する(コンプライ)か、遵守が出来ない場合はその理由を説明する(エクスプレイン)義務があることを差します。
したがって、ルールを一律強制して遵守させるわけではなく、原理原則を十分に理解したうえで、それでもなお実施が適切でない、遵守できない場合においては、その理由を説明することが求められる事を指します。
コンプライ・オア・エクスプレインとコンプライアンス
コンプライ・オア・エクスプレインはコンプライアンスへの対応をしているものです。コンプライアンスとは、事業や会社における法令遵守を指しますが、規制することで保護・確保されるべき企業の利益を実現していくことが目的となります。
一方で、コンプライ・オア・エクスプレインでは、事業を通じて利益の確保だけでなく社会的課題を解決していくために、組織の活動を最適化させるための仕組みづくりが目的となります。
以上を踏まえ、コンプライ・オア・エクスプレインは法令順守を目的として策定されていないということがポイントとなります。
コンプライ・オア・エクスプレインとコーポレートガバナンス・コード
コーポレートガバナンス・コードは、企業が顧客、株主などのステークホルダー側に立ち、透明性を確保し公正な意思決定を行うための土台となる基本的な原則やガイドラインをまとめたものです。これは、5つの基本原則を軸として設計された原則と補充原則により構成されています。
基本原則は、ガバナンスの充実で達成すべき理念や目標を定めた規範を示しており、5つの基本原則を実現していくにあたり、考慮してかなければならないことをまとめたものが原則として定められています。また、補充原則については、原則の内容がより具体的に表記されたものとなります。
なお、コーポレートガバナンス・コードについては、別の記事で詳細にご紹介しているので、そちらも併せてご覧ください。
⇒コーポレートガバナンス(企業統治)とは?目的・強化方法・歴史的背景について解説!
⇒コーポレートガバナンス・コードとは?概要・特徴・制定された背景について解説
⇒コーポレートガバナンス・コードの5つの基本原則|特徴・制定の背景・適用範囲と拘束力について解説
⇒【2021年改訂】コーポレートガバナンス・コードの実務対応と開示事例
⇒スチュワードシップ・コード|特徴・原則と責任・8つの基本原則と実施方法・メリット・デメリットについて解説
⇒プリンシプルベース・アプローチ|ルール・ベース・アプローチとの比較・背景・意義について解説
このコーポレートガバナンス・コードにおいて、採用されているものがコンプライ・オア・エクスプレインです。そのため、コーポレートガバナンス・コードにおける原則を遵守しない場合は、その理由を説明する必要が生じます。
コンプライ・オア・エクスプレインの意義

コンプライ・オア・エクスプレインの方式であることから、コーポレートガバナンス・コードの原理原則に対して完全なる遵守を求めていないことから、会社・組織ごとでどこまでの範囲を遵守して対応していくのか、柔軟性を持たせることができるようになります。
また、コーポレートガバナンス・コードの原理原則を遵守しない組織・会社においては、説明が求められることから、単なる勧告と比較すると順守に対して強い推進力を与えることができます。
また、コンプライをすることは、コーポレートガバナンス・コードに則り、組織・会社の経営をするにあたり、社会的にも一定のコンセンサスを得た行動基準を実施させることができるという意義があります。そのため、投資家や社会全体から信用を得ることができ、組織拡大に繋がっていくことになります。
次に、エクスプレインはコンプライすることが組織・会社の状況と照らし合わせて適切でない場合、事業活動を進めるにあたって最も良い施策を実施することができるという点に大きな意義が生じます。
コンプライ・オア・エクスプレインの対象範囲
コーポレートガバナンス・コードは、上場している全ての会社に対して適用されていることから、コンプライ・オア・エクスプレインにおいても同様に、すべての上場企業が対象の範囲となります。
ただし、上場している証券取引所の市場区分に応じて、コンプライ・オア・エクスプレインの対象となる基本原則・原則・補充原則の範囲が異なります。それは、コーポレートガバナンス・コードで定められる原則が、上場企業の分類に応じて異なっているためです。
東証の上場企業には、プライム市場・スタンダード市場・グロース市場の3つの市場(旧東証一部、東証二部、マザーズ、JASDAQ)がありますが、それぞれのコンプライ・オア・エクスプレインの適用となる範囲については以下の通りとなります。
| 市場 | 内容 |
|---|---|
| プライム市場・スタンダード市場 | ・コーポレートガバナンス・コードの全原則の適用 ・全ての原則にコンプライ・オア・エクスプレインを適用 |
| グロース市場 | ・各種補充原則等を除いた基本原則の部分のみ適用 ・補充原則にコンプライ・オア・エクスプレインの適用は及ばない |
グロース市場については、こちらの記事もご参照ください。
⇒グロース市場とは?市場区分の再編による変化を徹底解説!
上場準備企業等におけるコンプライ・オア・エクスプレインの必要性
上場準備企業(IPO企業)は、株式を新規に証券取引所に上場させることを目指している企業を指しますが、これらIPO準備企業においては、コンプライ・オア・エクスプレインの適用範囲外となります。
しかし、上場を目指している場合は、今後コーポレートガバナンス・コードへの対応が必要となってくるため、コーポレートガバナンス・コードが定める原理原則を認識し、コンプライ・オア・エクスプレインできるように準備していく必要があります。
上場については、こちらの記事もご参照ください。
⇒IPOのメリット・デメリットとは?企業・株主・従業員の観点で解説
⇒ベンチャー企業がIPOする意義はあるのか?上場のメリット・デメリット
⇒IPOの準備スケジュール|直前前々期から申請期まで解説
⇒上場の条件とは?上場基準・上場までの流れ・上場のポイントを徹底解説!
⇒上場のために必要な売上基準とは?IPOのための業績について解説
⇒上場審査とは?審査基準・審査の流れ・審査通過のポイントを徹底解説!
⇒IPOの失敗を防ぐには?IPO失敗理由・失敗事例・失敗の回避方法を解説
⇒上場ゴールとは?上場ゴールに陥らないためのポイントを詳しく解説
⇒IPOコンサルティングの種類や業務とは?必要なコストや選ぶ際のポイントも徹底解説!
コンプライ・オア・エクスプレインを守らない場合
コンプライ・オア・エクスプレインは法令に基づいたものではなく、東証における内部規程(コーポレートガバナンス・コード)にあたるため、罰せられたり違法とみなされる訳ではありません。
しかしながら、コンプライしない理由をエクスプレインしない場合や、コンプライした内容において虚偽の事実が認められた場合は、実効性確保措置の対象となります。
実効性確保措置とは、有価証券上場規程の第5章に定められている特設注意市場銘柄への指定や改善報告書の徴求、公表措置、上場契約違約金の支払いなどを指します。
エクスプレインの内容

コーポレートガバナンス・コードでは、既に述べている通り、各組織・会社の実情にあわせて適切でないと考えられる場合は、実施しない理由を十分にエクスプレインする必要があります。
そのため、自社の考えや方針、実情を投資者に理解されるような方法でエクスプレインする必要があります。ここでは、エクスプレインする場合に重要となるポイントをご紹介します。
・実施していない内容を明確に示す
・実施しない理由を説明する
・具体的な検討状況を説明する
実施していない内容を明確に示す
1つ目は、実施していない内容を明確に示すことです。また、ある特定の原則に対して、実施しているものとしていないものがある場合は、それらを明確に示す必要があります。
実施しない理由を説明する
2つ目は、実施していない内容について、なぜ現時点で実施していないのか、実施しないことが自社にとって適切であるかを説明することです。その際、自社の規模や特性、外部環境など自社の個別事情について説明すると良いでしょう。
また、別の手段をとっている場合は、具体的な実施内容や、なぜその手段をとったのか、適切であると考えた理由を明確に示しましょう。
具体的な検討状況を説明する
最後は、これからコーポレートガバナンス・コードを実施していく場合、具体的な検討状況を説明することです。検討するにあたり、どのような体制で進めていくのか、またその手法やプロセス、今検討している要素などを示しましょう。
また、検討の進捗状況や実施に至るまでのスケジュールも示すと良いでしょう。また、経過的に取り組んでいる事があれば、その内容についても記載するようにしましょう。
不十分なエクスプレイン
コーポレートガバナンス・コードを遵守出来ない場合のエクスプレインについて、不十分な内容と考えられる事例の特徴を3種類に分類してご紹介します。
・対応状況が不明確
・実施しない理由が不明確
・抽象的な説明
対応状況が不明確
1つ目は、対応状況が不明確なエクスプレインです。実施していない内容が十分に記載されていないことで不明確なものとなり、エクスプレインとした理由が曖昧であるものを挙げることができます。
実施しない理由が不明確
2つ目は、実施しない理由が不明確なエクスプレインです。実施しない理由を明確に記載せず、具体的な現状の検討状況も示さずに、ただ検討すると記載しているエクスプレインについても不十分なものとして考えられます。
抽象的な説明
最後は、抽象的な説明となっているエクスプレインです。具体的な内容を明記せず、コーポレートガバナンス・コードの文言を抽出し記載していることで、抽象的な説明となってしまっているエクスプレインも不十分なものとなります。
また、自社においてなぜできないのか、という具体的な個別事情を記載していない内容も抽象的なものとなり、十分なエクスプレインとはみなされません。
エクスプレインの方法

エクスプレインの方法については、特段決まりや指定はありません。具体的な例としては、プレスやホームページ、株主総会の資料などが挙げられます。開示方法を検討する際に重要なポイントは、誰にどのような情報を公開するのか、そのためにはどのようなアプローチがあるのかを考えて実施するようにしましょう。
また、エクスプレインするにあたり、上述したエクスプレインするポイントを踏まえて、どの原則について遵守していないのかを明確にし、その理由を記載するようにしましょう。情報の開示という形で遵守することが必要となるため、項目別にして記載すると良いでしょう。
コンプライのための情報開示
コーポレートガバナンス・コードをコンプライするために開示が必要となる情報もあります。こちらについても、エクスプレインと同じようにコーポレートガバナンス・コードにおいて、開示を行うべきであると記載されています。コンプライするために情報を開示しなくてはならない原則については、以下の通りです。
| 原則 | 開示すべき概要 |
|---|---|
| 原則 1-4 | 政策保有株式として上場株式を保有する場合、政策保有に関する方針や議決権の行使に関して適切な対応を確保するための基準 |
| 原則 1-7 | 関連当事者間の取引を行う場合、該当する取引についての重要性やその性質に応じた適切な手段を決める枠組み |
| 原則 3-1 | ①経営理念等、経営戦略、経営計画 ②コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方・基本方針 ③経営陣幹部・取締役報酬等の決定方針・手続 ④経営陣幹部選任・取締役等指名の方針・手続 ⑤経営陣幹部選任・取締役等指名の際の個々の選任・指名についての説明 |
| 補充原則 4-1① | 経営陣に対する委任の範囲 |
| 原則 4-8 | 自主的な判断に基づいて、少なくとも3分の1以上の独立社外取締役を選任することが必要と考える上場会社は、そのための取組み方針 |
| 原則 4-9 | 独立社外取締役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼をおいた独立性判断基準 |
| 補充原則 4-11① | 取締役会全体の知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 |
| 補充原則 4-12② | 取締役・監査役が他の上場会社の役員を兼任する場合、その兼任状況 |
| 補充原則 4-11③ | 取締役会全体の実効性に関する分析と評価結果の概要 |
| 補充原則 4-14② | 取締役・監査役に対する研修方針 |
| 原則 5-1 | 株主との建設的な対話促進に向けた体制の整備及び取組みに関する方針 |
出典:CGコード開示の動向①「コンプライ・オア・エクスプレイン」の現況(大和総研)
出典:コーポレートガバナンス・コードの全原則適用に係る対応について
まとめ
本記事では、コンプライ・オア・エクスプレインの考え方や必要性・意義、対象範囲、また具体的な内容についてご紹介しました。コーポレートガバナンス・コードで示された原則は、必ずしも遵守しなければならないものではなく、自社にとって適切では無いと考えられる場合は遵守しないという選択肢もありますが、その理由を明確に説明しなければなりません。
コンプライ・オア・エクスプレインの意義や目的を十分に理解したうえで、適切なエクスプレインを果たしていくことが重要となりますので、エクスプレインにおけるポイントを十分に理解しておくようにしましょう。
本記事が、経営者・役員・企業のガバナンスに関係する担当者の方の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
ガバナンスに関連する内容であるTCFDについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒TCFDとは?気候関連財務情報開示タスクフォースの概要・TCFDに関する世界的な取組について解説
⇒TCFDの4つの主要な開示要件|ガバナンス・戦略・リスク管理・指標と目標について詳細に解説
⇒TCFDの開示内容の具体例|金融機関が発行するTCFDレポートを中心に解説
⇒TCFDコンソーシアム|組織構成と設立背景・活動指針・活動内容について丁寧に解説
⇒TCFD賛同企業|TCFDコンソーシアム企業の具体的な取り組み事例も紹介
⇒TCFDのシナリオ分析とは?分析の手順・分析の上で理解すべきポイントを解説
⇒プライム市場におけるTCFDの開示の義務化|コーポレートガバナンス・コードの改訂を背景にした情報開示の今後の見通しも解説
⇒TCFDコンサルティング|外部コンサルタントに依頼するメリット・コンサルの進め方について解説
また、ESGについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒ESGとは?ESG概要や注目された背景、メリットや課題点まで網羅的に解説!
⇒ESG経営とは?必要性や戦略・メリット・具体例をわかりやすく解説
⇒ESG経営の取り組み事例集!企業ごとの具体例を紹介
⇒ESGコンサル会社とは?役割や依頼先企業の選び方などを解説
また、株式報酬制度のご導入やコーポレートガバナンス・コードへの対応を検討をするには、プロの専門家に聞くのが一番です。
そこでSOICOでは、個別の無料相談会を実施しております。
・自社株式報酬制度を導入したいがどこから手をつければいいか分からない
・CGコードや会社法改正を踏まえた株式報酬制度の設計は具体的にどうすべきか分からない
そんなお悩みを抱える経営者の方に、要望をしっかりヒアリングさせていただき、
適切な情報をお伝えさせていただきます。
ぜひ下のカレンダーから相談会の予約をしてみてくださいね!
この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。