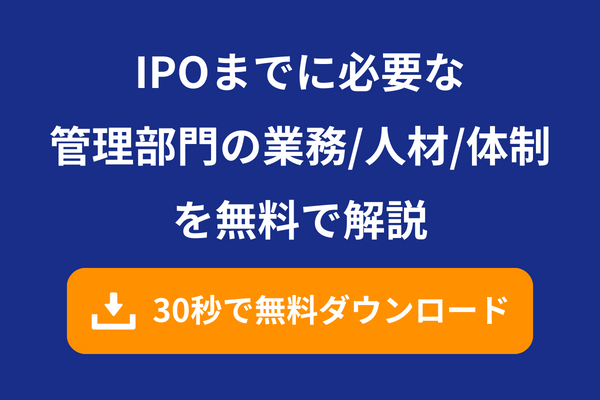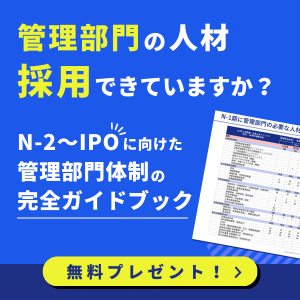COLUMN
コラム
上場の条件とは?上場基準・上場までの流れ・上場のポイントを徹底解説!
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)



『資金調達の手引き』
調達ノウハウを徹底解説
資金調達を進めたい経営者の方の
よくある疑問を解決します!
スタートアップ・ベンチャー企業の経営者の中には、自社の上場を目指しているものの、実際に上場するためには何をすればよいか分からないという方も多くいらっしゃることかと思います。
そこで、今回の記事では、
・上場(IPO)とは
・上場のメリット
・上場のデメリット
・上場基準とは
・各市場の上場基準
・上場までの流れ
・上場に向けておさえるべきポイント
について解説していきます。
目次
上場(IPO)とは
上場(IPO)とは、未上場企業が新規に株式を証券取引所に上場させることで、自社の株式を一般投資家の間でも売買できるようにすることをいいます。
IPOは「Initial(最初の)Public(公開の)Offering(売り物)」の略です。
上場前までは、新株発行と資金調達の対象が創業者自身やVCなどの一部の投資家に限定されていますが、上場後は誰でも株式が購入できるようになります。
上場すると、一般投資家が安心して株式を売買できるように、事業の継続性や経営の透明性が求められるため、上場前には求められることがなかった事項や費用が発生します。
しかし、上場することで、
・上場前の段階では調達できないほど大きな金額を調達できるようになる
・知名度及び社会的信用力の向上によって販売先、取引先が増える
・優秀な人員を採用しやすくなる
など、多くのメリットが得られます。以下詳しく見ていきましょう。
上場のメリット
上場するメリットとしては以下があげられます。
・知名度・社会的信用が向上する
・資金調達の選択肢が増える
・優秀な人材を採用しやすくなる
・創業者利益を確保できる
上場は企業に多くのメリットをもたらします。
そのため、上場を目指す経営者の方も多いことでしょう。
上場のメリットについては、次の記事もご参照ください。
⇒IPOのメリット・デメリットとは?企業・株主・従業員の観点で解説
知名度・社会的信用が向上する
日本には企業が370万社ほどありますが、このうち、上場企業は3,800社程度しか存在しません。
つまり、上場するということはこの約0.1%に選ばれることを意味しており、上場することによって会社の知名度・社会的信用力を向上させることが可能です。
知名度・社会的信用力向上に伴い、金融機関の信頼性も向上すれば、結果的に資金調達力も向上させることが可能です。
資金調達の選択肢が増える
上場すると、さまざまな形で資金調達を行えるようになります。
上場するためには厳しい基準をクリアしなければならないため、上場企業は信頼できる企業と言い換えることもできるため、上場前にはハードルの高かった金融機関(銀行)からの資金調達もしやすくなります。
また、株式を新規発行したり、既存の株式を売ることで一般投資家からも資金調達が可能です。
資金調達により、自己資本が充実させて財務体質を強化すれば、
・新設備の導入
・優秀な従業員の採用
・新規事業の立ち上げ
などを通して、スピード感を持って企業成長が可能になります。
資金調達については、こちらの記事もご参照ください。
⇒ベンチャー・スタートアップの資金調達方法とは?投資ラウンド別・調達事例を含めて徹底解説!
⇒資金調達の手段・方法には何がある?それぞれのメリット・デメリットも徹底解説!
⇒返済不要な資金調達とは?メリットやデメリット、調達時の注意点を徹底解説!
優秀な人材を採用しやすくなる
上場は、企業の信用力の向上にもつながるため、採用活動において優秀な人材を獲得しやすくなります。
採用サイトや転職サイトでは、検索条件に「上場企業」という項目が設けられているケースが多いです。
つまり、上場することによって、信頼できる企業で働きたいと考える優秀な人材を採用しやすくなるといえます。
創業者利益を確保できる
創業者は、上場後株式を売却することで、投下した資本を回収し創業者利益を確保することができます。
また、株式が証券取引所で流通し、公正な株価が形成されることで、株式の換金性が高まり、創業者をはじめとした株主の財産形成につながります。
上場のデメリット
上場は企業にさまざまなメリットをもたらしますが、注意しておくべきデメリットもあります。
具体的には以下があげられます。
・敵対的買収(TOB)をされる恐れがある
・上場コストが発生する
・株主対応が必要になる
上場を目指す際はこれらのデメリットも把握しておきましょう。
敵対的買収(敵対的TOB)をされる恐れがある
上場すると、株式市場で誰でも自由に自社の株式を売買できるようになりますので、当然ながら競合他社に株式を買い占められ、経営権を奪われてしまうリスクも生じます。
買収先の同意を得ない強制的な買収は、敵対的買収(敵対的TOB※)と呼ばれています。
※TOB:Take-Over Bidの略
経営権の横取りを目的とする株式の買収が発生した際に、どのように防衛対策をとるのか、上場前の段階から検討することをおすすめします。
上場コストが発生する
上場後は以下のようなコストが発生します。
| 費用の種類(支払先) | 金額の目安 |
|---|---|
| 年間上場料(証券取引所) | 50万円~450万円程度 |
| 監査報酬(監査法人) | 800万円~2,000万円程度 |
| 株式事務代行手数料 (株主名簿管理人の信託銀行) |
300万円~400万円程度 |
上記以外にも、上場を維持するうえで、開示体制を確立するためのコストやであったり、株主総会の運営やIRに関するコスト等も継続して発生します。
株主対応が必要になる
上場企業では、経営者の独断で事業を運営することはできず、不特定多数の株主の思いを汲み取る必要があります。
株主には、経営方針等について経営陣に意見する権利があるため、上場した場合、企業の所有者ともいえる不特定多数の株主の意見を考慮しなければなりません。
具体的には、会社法の定めにより、株主総会を1年に1度開催することが義務付けられています。
株主総会開催には、
・会場費
・株主の招集通知および同封する事業報告書
・計算書類等の印刷費
・郵送費
・人件費
など様々なコストが発生します。
上場基準とは
上場するためには、証券取引所に申請して、審査を通過する必要があります。
審査を通過するためには、証券取引所が定めている基準を満たすことが求められ、この基準を上場基準といいます。
上場基準には、「①形式要件」と「②実質審査基準」があります。
なぜ、上場には条件が設定されているのでしょうか。
仮に、株式の上場に対して厳しい条件が設定されていなかった場合、「上場後すぐに倒産してしまう」「業績や財務内容に虚偽があり上場適格でない企業も上場してしまう」などのケースが想定されます。
このような状態では、投資家が安心して株式を売買できなくなる恐れがあるため、証券取引所によって厳しい条件が設定され、審査が行われます。
①形式要件
企業が上場するためには、まず形式要件を満たす必要があります。
形式要件は形式基準とも呼ばれており、「受付基準」と「不受理事項」の2つに分けられます。
要件は証券取引所や市場によって異なりますが、財務数値や株主数、株式数などの数値を達成していることが必要です。
上場申請のために提出された資料などで判断されます。
受付基準
受付基準は、上場のために最低限満たしておかなくてはならない基準のことをいいます。
各市場にはそれぞれ異なる受付基準があり、主に以下の内容について基準が設けられています。
・株主数
・流動株式数
・流通株式時価総額
・時価総額
・流通株式比率
・収益基盤
・財政状態
・公募
・事業継続年数
・その他
不受理事項
形式要件は満たしていても、企業が不受理事項に当てはまる場合は受理が取り消されます。
不受理事項は以下のとおりです。
1.合併・会社分割・子会社化もしくは非子会社化・事業の譲受もしくは譲渡する予定のある場合
2.合併・株式交換または株式移転をする予定のある場合
3.上場前に第三者割当増資などによる募集株式などの割当などの確約を提出しない場合、また割当を受けたものが所有していない場合
1は、上場申請した日の直前事業年度の末日から2年以内に予定がある場合が該当します。
また、上場を申請した会社がそれによって実質的に存続できなくなっていると認める場合も当てはまります。
さらに、上場を申請した会社の子会社が行う、もしくは行う予定がある場合も含まれるので注意しましょう。
2も、上場申請した日の直前事業年度の末日から2年以内に予定がある場合が該当しますが、上場日前に行う場合は当てはまりません。
②実質要件(実質審査基準)
形式要件を満たしたうえで上場を審査する基準になるのが実質審査基準です。
実質審査基準も各市場によって内容は異なりますが、形式基準ほど各市場ごとの違いはありません。
実質審査基準で判断されるものは、以下のとおりです。
・企業の継続性・収益性
・企業経営の健全性
・コーポレートガバナンス・内部管理体制の有効性
・企業情報の開示が適切か
企業の継続性・収益性
合理的な事業計画が作成されていて、かつ、企業が継続して安定した収益をあげることができると見込まれる状態かどうかが審査されます。
継続性や収益性が満たされていなければ、上場に適していないと判断される場合もあります。
適切な事業計画には、事業基盤が適切に整備されている、もしくは、整備される見込みがあることが必要です。
また、事業環境やリスク管理にも漏れなく対応していることが求められます。
企業経営の健全性
株主の利益を保護するためには、事業が公正かつ忠実に行われている必要があります。
この点も審査されます。
一例として、企業が以下のような状況にある場合は公正ではないと判断されます。
・取引行為等の経営活動で不当な利益を享受もしくは供与しているといった状況
・親族が役員を行っており、勤務実態・他の会社との兼務状況が公正でなく、職務や監査の実施を毀損するような状況
・親会社が存在し、企業グループの経営が親会社から独立性を有するような状態
コーポレートガバナンス・内部管理体制の有効性
コーポレート・ガバナンスや内部管理体制が適切に整備されて機能しているかが審査されます。
具体的には、以下のような状態であることが求められます。
・役員が適切に職務を遂行するための体制が適切に整備・運営されている
・内部管理体制が適切に整備・運営されている
・安定かつ継続的に内部管理体制を維持するための人員が確保されている
・会計処理が適切に整備・運用されている
・法令などを守るための体制が適切に整備・運営されており、法令違反を起こしていない
コーポレートガバナンスコードについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒コーポレートガバナンス(企業統治)とは?目的・強化方法・歴史的背景について解説!
⇒コーポレートガバナンスコードの5つの基本原則|特徴・制定の背景・適用範囲と拘束力について解説
⇒【2021年改訂】コーポレートガバナンス・コードの実務対応と開示事例
企業情報の開示が適切か
投資家は会社情報を見て投資するかどうかを決めるため、企業は十分な会社情報を開示する必要があります。
そのため、情報を開示できる体制を構築し、情報管理が適切に行われているかが審査されます。
例えば、以下の状態にあることが求められます。
・会社情報が適切に管理されていて、投資家に随時開示可能な状態
・開示に関する書類が法令に準じて作成されていて、適切に記載されている状態
・取引や株式の所有割合等によって、企業グループの開示で不正を働いていない状態
・親会社がある場合は、申請会社の経営に影響を及ぼす情報が適切に開示されている状態
企業情報開示については、次の項目もご参照ください。
⇒TCFDとは?気候関連財務情報開示タスクフォースの概要・TCFDに関する世界的な取組について解説
⇒ISO30414とは?注目された背景・目的・具体的内容・情報開示のポイントを解説
各市場の上場基準
2022年4月4日、東京証券取引所の市場区分が見直され、現在は以下3つの市場が存在しています。
・プライム市場
・スタンダード市場
・グロース市場
以下で各市場の上場基準について紹介します。
プライム市場
プライム市場の形式要件は以下の通りです。
| 項目 | プライム市場への新規上場 |
|---|---|
| (1)株主数(上場時見込み) | 800人以上 |
| (2)流通株式(上場時見込み) | 流通株式数 2万単位以上 流通株式時価総額 100 億円以上 流通株式比率 35%以上 |
| (3)時価総額(上場時見込み) | 250 億円以上 |
| (4)純資産額(上場時見込み) | 連結純資産の額が 50 億円以上で、単体純資産の額が負でないこと |
| (5)利益の額は売上高 | 以下のaまたはbに適合すること a.最近2年間の利益の額の総額が 25億円以上であること b.最近1年間における売上高が 100 億円以上である場合で、 時価総額が 1,000 億円以上となる見込みがあること |
| (6)事業継続年数 | 3年以上前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること |
| (7)虚偽記載または不適正意見等 | a.最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし b.最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」または「除外事項を付した限定付適正」 c.最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」 d.新規上場申請に関する株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合、次の(1)及び(2)に該当するものでないこと (1)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載 (2)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載 |
| (8)上場会社監査事務所による監査 | 最近2年間の財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査等を受けていること |
| (9)株式事務代行機関の設置 | 東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、または当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
| (10)単元株式数 | 単元株式数が、100株となる見込みのあること |
| (11)株券の種類 | 新規上場申請に関する株券等が、次のaからcのいずれかであること a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式 b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式 c.無議決権株式 |
| (12)株式の譲渡制限 | 新規上場申請に関する株式の譲渡につき制限を行っていないこと、または上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること |
| (13)指定振替機関における取扱い | 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること、または取扱いの対象となる見込みのあること |
| (14)合併等の実施の見込み | 次のa及びbに該当しないこと a.新規上場申請日以後、同日の直前事業年度の末日から2年以内に、合併、会社分割、子会社化・非子会社化、もしくは事業の譲受け・譲渡を行う予定があり、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合 b.申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換または株式移転を新規上場申請日の直前事業年度の末日から2年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く。) |
プライム市場の実質審査基準は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| (1)企業の収益性・継続性 | 継続的に事業を営み、安定し優れた収益基盤を有していること |
| (2)企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |
| (3)企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること |
| (4)企業内容等の開示の適正性 | 企業内容等を適切に開示できる状況にあること |
| (5)その他公益または投資者保護の観点から東京証券取引所が必要と認める事項 | – |
スタンダード市場
スタンダード市場の形式要件は以下の通りです。
| 項目 | スタンダード市場への新規上場 |
|---|---|
| (1)株主数(上場時見込み) | 400人以上 |
| (2)流通株式(上場時見込み) | 流通株式数 2,000単位以上 流通株式時価総額 10 億円以上 流通株式比率 25%以上 |
| (3)事業継続年数 | 3年以上前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること |
| (4)純資産額(上場時見込み) | 連結純資産の額が正であること |
| (5)利益の額 | 最近1年間の利益の額が1億円以上であること |
| (6)虚偽記載または不適正意見等 | a.最近2年間の有価証券報告書等に「虚偽記載」なし b.最近2年間(最近1年間を除く)の財務諸表等の監査意見が「無限定適正」または「除外事項を付した限定付適正」 c.最近1年間の財務諸表等の監査意見が原則として「無限定適正」 d.新規上場申請に関する株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合、次の(1)及び(2)に該当するものでないこと (1)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載 (2)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載 |
| (7)上場会社監査事務所による監査 | 最近2年間の財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査等を受けていること |
| (8)株式事務代行機関の設置 | 東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、または当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
| (9)単元株式数 | 単元株式数が、100株となる見込みのあること |
| (10)株券の種類 | 新規上場申請に関する株券等が、次のaからcのいずれかであること a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式 b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式 c.無議決権株式 |
| (11)株式の譲渡制限 | 新規上場申請に関する株式の譲渡につき制限を行っていないこと、または上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること |
| (12)指定振替機関における取扱い | 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること、または取扱いの対象となる見込みのあること |
| (13)合併等の実施の見込み | 次のa及びbに該当しないこと a.新規上場申請日以後、同日の直前事業年度の末日から2年以内に、合併、会社分割、子会社化・非子会社化、もしくは事業の譲受け・譲渡を行う予定があり、申請会社が当該行為により実質的な存続会社でなくなる場合 b.申請会社が解散会社となる合併、他の会社の完全子会社となる株式交換または株式移転を新規上場申請日の直前事業年度の末日から2年以内に行う予定のある場合(上場日以前に行う予定のある場合を除く。) |
スタンダード市場の実質審査基準は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| (1)企業の収益性・継続性 | 継続的に事業を営み、安定し優れた収益基盤を有していること |
| (2)企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |
| (3)企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること |
| (4)企業内容等の開示の適正性 | 企業内容等を適切に開示できる状況にあること |
| (5)その他公益または投資者保護の観点から東京証券取引所が必要と認める事項 | – |
グロース市場
グロース市場の形式要件は以下の通りです。
| 項目 | グロース市場への新規上場 |
|---|---|
| (1)株主数(上場時見込み) | 150人以上 |
| (2)流通株式(上場時見込み) | 流通株式数 1,000単位以上 流通株式時価総額 5億円以上 流通株式比率 25%以上 |
| (3)公募の実施 |
500単位以上の新規上場申請における株券等の公募を行うこと |
| (4)事業継続年数 | 1年以上前から取締役会を設置して、継続的に事業活動をしていること |
| (5)虚偽記載または不適正意見等 | a.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書(最近1年間を除く)において、「無限定適正」または「除外事項を付した限定付適正」 b.「上場申請のための有価証券報告書」に添付される監査報告書等(最近1年間) において、「無限定適正」 c.上記監査報告書または 四半期レビュー報告書に係る財務諸表等が記載又は参照される有価証券報告書等に「虚偽記載」なし d.新規上場申請に関する株券等が国内の他の金融商品取引所に上場されている場合、次の(1)及び(2)に該当するものでないこと (1)最近1年間の内部統制報告書に「評価結果を表明できない」旨の記載 (2)最近1年間の内部統制監査報告書に「意見の表明をしない」旨の記載 |
| (6)上場会社監査事務所による監査 | 「新規上場申請のための有価証券報告書」に記載及び添付される財務諸表等について、上場会社監査事務所の監査等を受けていること |
| (7)株式事務代行機関の設置 | 東京証券取引所の承認する株式事務代行機関に委託しているか、または当該株式事務代行機関から株式事務を受託する旨の内諾を得ていること |
| (8)単元株式数 | 単元株式数が、100株となる見込みのあること |
| (9)株券の種類 | 新規上場申請に関する株券等が、次のaからcのいずれかであること a.議決権付株式を1種類のみ発行している会社における当該議決権付株式 b.複数の種類の議決権付株式を発行している会社において、経済的利益を受ける権利の価額等が他のいずれかの種類の議決権付株式よりも高い種類の議決権付株式 c.無議決権株式 |
| (10)株式の譲渡制限 | 新規上場申請に関する株式の譲渡につき制限を行っていないこと、または上場の時までに制限を行わないこととなる見込みのあること |
| (11)指定振替機関における取扱い | 指定振替機関の振替業における取扱いの対象であること、または取扱いの対象となる見込みのあること |
グロース市場の実質審査基準は以下の通りです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| (1)企業内容、リスク情報等の開示の適切性 | 企業内容、リスク情報等の開示を適切に行うことが可能な状況にあること |
| (2)企業経営の健全性 | 事業を公正かつ忠実に遂行していること |
| (3)企業のコーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の有効性 | コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制が適切に整備され、機能していること |
| (4)事業計画の合理性 | 合理的な事業計画を策定しており、その事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること、または整備する合理的な見込みのあること |
| (5)その他公益または投資者保護の観点から東京証券取引所が必要と認める事項 | – |
グロース市場については、こちらの記事もご参照ください。
⇒グロース市場とは?市場区分の再編による変化を徹底解説!
上場までの流れ
実際に上場するまでの流れについて解説します。
上場の実現に向けて最低でも3年前から準備を行うケースが一般的です。
上場のスケジュールについては、ことらの記事もご参照ください。
⇒IPOの準備スケジュール|直前前々期から申請期まで解説
上場から3期前
上場することを決定した場合、まず監査法人によるショートレビューを受ける必要があります。
ショートレビューは予備調査ともいいます。
上場するために準備すべき事項を確認したり、改善の必要がある事項を指摘してもらったりするための調査です。
また、メインバンクやベンチャーキャピタル、証券代行機関、印刷会社、顧問弁護士、コンサルティング会社など、多数の関係者と密接に連携し、協力して準備を進めることになります。
上場コンサル・監査法人・ショートレビューについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒IPOコンサルティングの種類や業務とは?必要なコストや選ぶ際のポイントも徹底解説!
⇒IPOにおける監査法人の役割とは?監査法人を選ぶポイントも解説!
⇒IPOに向けたショートレビューとは?費用・時期・確認するポイントも解説!
上場から2期前
期初に監査法人による調査を受けることで、監査を受ける体制を整備します。
また、期末が過ぎたら再度監査を受け、適正であるという評価(※適正意見といいます)を受ける必要があります。
財務会計の他、各種規程の整備、社内システム・関連会社取引の見直し等、前年度のショートレビューで指摘された事項が適切に改善されているかが確認されます。
適切に実施されていない場合は、もう1年時間をかけて適切に運用されるよう実施する必要があります。
また、この時期には主幹事証券会社を決定し、各種申請書類の作成など審査に向けた準備を始めておくことが望ましいです。
上場から1期前
監査法人や証券会社の指導を受けながら、取締役会などの運営体制、会計管理、労務管理、社内規則の徹底、ディスクロージャー体制等、上場に必要なルールや体制が整備されているか最終的な確認と実施を繰り返し行います。
また、上場申請書類や投資家向け説明資料などの原稿を作成し、監査法人や証券会社の指導を受けます。
この期でも監査法人の監査を受け適正意見を得る必要があります。
上場の直前期(N-1期)については、こちらの記事をご参照ください。
⇒上場スケジュール:直前期 〜直前期(N-1期)の過程について解説〜
上場年度
申請書類等一式を最終的に完成させて、証券取引所に上場の申請をします。
証券取引所の上場審査には2ヶ月から3ヶ月程度時間がかかります。
複数回の現地調査や代表者へヒアリングなどを経て、証券取引所から上場承認がおりた場合、無事に上場ができます。
上場年度・申請期については、こちらの記事もご参照ください。
⇒上場スケジュール:申請期 〜申請期の過程について解説〜
上場に向けておさえるべきポイント
上場に向けておさえるべきポイントとしては以下があげられます。
・自社にあった市場を選択する
・人事労務の見直し・改善する
・不受理事項に該当しないように注意する
上場を検討している企業の経営者はこちらを踏まえて社内体制を整えておくとよいでしょう。
自社にあった市場を選択する
2022年に市場区分が見直されたことによって上場基準にも変化があり、各市場のコンセプトが明確に打ち出されました。
各市場のコンセプトから、自社が今どの位置にあるかを把握し、上場する市場を選択するとよいでしょう。
一般的に、上場前の会社はグロース市場への上場を目指すことが多いです。
以下、各市場のコンセプトを説明します。
【プライム市場】
多くの機関投資家の投資対象になれる規模の時価総額(流動性)を持っていて、より高いガバナンス水準を備え、投資家との建設的な対話を中心に据えて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努める企業向けの市場がプライム市場です。
【スタンダード市場】
投資対象として一定の時価総額(流動性)を持っている企業向けの市場です。上場企業として基本的なガバナンス水準を持ちつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努める企業向けの市場であるといえます。
【グロース市場】
高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適切な開示が行われ、一定の市場評価が得られる市場です。ただ、事業実績から見るとリスクが高い傾向がある市場といえます。
プライム市場のガバナンスについて、こちらの記事もご参照ください。
⇒プライム市場におけるTCFDの開示の義務化|コーポレートガバナンス・コードの改訂を背景にした情報開示の今後の見通しも解説
人事労務の見直し・改善をする
人事労務は、社内における組織や管理・統制およびコンプライアンス等に関わる業務です。
上場の際、経営者は売上・利益の確保や事業の継続性には目を向けますが、社内統制などについてはあいまいにしたり、見落としがちです。
しかし、上場する際は、就業規則の整備や残業代の未払い、訴訟の有無等を指摘されるケースもあります。
上記のような問題は事前に改善しておくことが望ましいでしょう。
IPOにおける労務監査・就業規則について、こちらの記事もご参照ください。
⇒IPOに向けた労務監査とは?労務管理のポイントについて解説
⇒就業規則の作成について|就業規則の作成手順と記載事項・作成時の注意点も解説
不受理事項に該当しないように注意する
不受理事項に当てはまると上場は不可能です。
不受理事項には抵触しないように十分気をつける必要があります。
たとえば、上場時期を知っている人が短期利益を図る恐れがあることをどのように防止するのかについても事前に考え対策しておきましょう。
プロ投資家向けのTOKYO PRO マーケット
東京証券取引所には、ここまで説明してきた「グロース市場」「スタンダード市場」「プライム市場」に加えて、プロ投資家向けの「Tokyo Pro マーケット」が存在します。
Tokyo Pro マーケットは、上場のための形式要件がないことが他の3つの市場と違います。また、Tokyo Pro マーケットは、東京証券取引所の代わりに上場適正の評価や上場の手続き、上場後に適時開示の指導をする制度であるJ-Adviser制度を導入しています。この制度によって、内部管理体制および開示義務に対応できる組織体制が整備され、東京証券取引所に上場するに値する企業の質が担保されています。
Tokyo Proマーケットについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒東京プロマーケットとは?上場市場の選び方について解説
⇒東京プロマーケットへの上場は意味がない?市場の特徴とTPMに上場する意義を解説
まとめ
いかがでしたでしょうか。
今回は上場の条件や上場までの流れ、上場へ向けておさえておくべきポイントについて解説しました。
現在スタートアップ・ベンチャー企業を経営していて上場を検討されている方にとって参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます!
また、管理部門体制の構築をしたり、CFO人材の採用を進めたり、資金調達を加速させたりするには、プロの専門家に相談するのが一番です。
そこでSOICOでは、CFO中心とした管理部門組織の構築や、ファイナンスに長けたプロによる、個別の無料相談会を実施しております。
・CFOやバックオフィスの部長クラスが採用できている会社は、給与/役員報酬、株式報酬、採用手法は具体的にどうやっているか?
・今の自社の経営状態を踏まえた上で、資金調達を失敗しないために、どういったポイントを意識して進めるべきか?
そんなお悩みを抱える経営者の方に、要望をしっかりヒアリングさせていただき、
適切な情報をお伝えさせていただきます。
ぜひ下のカレンダーから相談会の予約をしてみてくださいね!
この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。