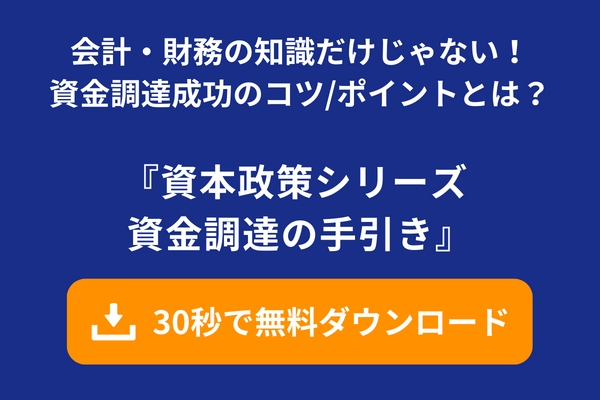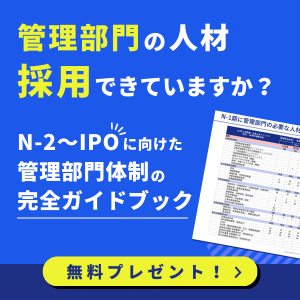COLUMN
コラム
【経営者・役員向け】上場スケジュール:直前期|直前期(N-1期)の過程について解説
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)



『資金調達の手引き』
調達ノウハウを徹底解説
資金調達を進めたい経営者の方の
よくある疑問を解決します!

上場を行うためには、証券取引所に申請を行い、証券取引所による審査を通過する必要があります。そのため、上場申請のために様々な準備が必要になります。
上場を行うための準備スケジュールの全体の概要については以下の記事で詳しく解説を行っています。
⇒【経営者・役員向け】IPOの準備スケジュール|直前前々期から申請期まで解説
本記事では上場準備の中でも、上場申請を行う前の期である直前期に行うことについて詳しく解説をしていきます。
IPOのスケジュール

IPOの準備には少なくとも3年ほどの期間がかかります。その理由は、上場直前2期分のIPO監査が必要であるからです。また、上場に向けて社内の体制を構築しなければならず、体制の構築に時間がかかることも理由としてあげられます。社内体制の中でも、上場後の経営管理体制の構築が重要であり、経営管理体制は構築されていることだけでなく、1年間適切に運用されていることが上場審査で審査されます。
社内の管理体制については、こちらの記事もご参照ください。
⇒内部統制とは?目的・会社法や金融商品取引法での定義や方針を徹底解説!
⇒IPOに内部統制が必要な理由とは?構築する目的・要素も解説!
⇒外部監査とは?内部監査との違い・外部監査の目的・監査プロセスを解説!
⇒コーポレートガバナンス(企業統治)とは?目的・強化方法・歴史的背景について解説!
このように、IPOには様々な準備が必要になるため、上場を行う際には上場のためのスケジュールを把握して早めの準備をしていくことが大切になります。
IPOの準備は、次のような期間に分けて考えられています。
・申請3期前:直前前々期(3期前、N-3期)
・申請2期前:直前々期(2期前、N-2期)
・申請1期前:直前期(1期前、N-1期)
・上場の申請:申請期
それぞれの期間に行うことの概要を説明します。
直前前々期(3期前、N-3期)はIPOに向けた会社の経営や事業の計画を立てる期間になります。直前前々期のはじめにIPOに向けた事業計画を立てます。そして、設計した事業計画を達成するための資金調達と株主構成の計画である資本政策を立案します。そのために、監査法人からショートレビューを受ける必要があります。ショートレビューを受けることで見つかったIPO課題を解消するために社内でプロジェクトチームを編成し課題解決に取り組み始めます。
ショートレビューについては以下の記事で詳しく解説を行っております。
⇒【経営者必読】IPOに向けたショートレビューとは?費用・時期・確認するポイントも解説!
直前々期(2期前、N-2期)からは会計監査が始まります。そのため、ショートレビューで指摘された問題点を全て解消する必要があります。そのため、直前々期には会計制度や業務管理制度を整備し、社内の管理体制を整えていきます。
直前期(1期前、N-1期)では株式上場の実現に向けて、実際に上場する市場を選定することや申請書類を作成したりすることをはじめ、文字通り、上場に向けた直前の準備期間として広範囲にわたる業務を並行して行います。
申請期にはまず、主幹事証券会社による引受審査を受けます。その後、上場申請を行うと、証券取引所による審査が行われます。この審査では多くの質問事項に対して迅速に回答することが求められます。同時に、会社が上場すると株式制限のない公開会社となることから、このタイミングで定款の変更も必要です。申請期に行われる審査が通ると上場に至ります。
申請期・主幹事証券会社については、こちらの記事もご参照ください。
⇒上場スケジュール:申請期|申請期の過程について解説
⇒主幹事証券会社とは?役割・選び方・変更について解説
⇒IPOにおける主幹事証券会社の選び方|主幹事選択の事例と証券会社について解説
⇒IPOにおける主幹事証券会社の役割|引受審査や選び方についても解説
IPOの準備スケジュールを大まかに述べると以上のような流れになります。本記事では、IPOの準備スケジュールの中の、「直前期(1期前、N-1期)」に行うことについて詳しく解説をしていきます。
直前期(N-1期)に行うこと
直前期(N-1期)に行うことをまとめると以下のものがあります。
①経営管理体制を運用する
②事業計画・資本政策を見直す
③市場を選定する
④申請書類を作成する
1. 経営管理体制を運用する
直前期は、これまでにIPOに向けて構築・整備してきた
・内部統制制度
・利益管理制度
・業務管理制度
・会計制度
・組織運営体制
といった経営管理体制が適切に運用していくことができるかを試すための期間になります。
上場審査の際には適切な経営管理体制が構築されているか、そして適切にそれらが運用されているかという点が重要になります。お試し期間であるこの時期に、構築・整備してきた経営管理体制に不備が見つかった場合には上場審査に通過しない可能性が非常に高いため、できるだけ早く改善をしていかなければなりません。
2. 事業計画・資本政策を見直す
申請期に行われる主幹事証券会社の引受審査や証券取引所の上場審査に向けて、事業計画・資本政策の見直しを行う必要があります。
資本政策はIPOに向け資金調達の方法や株主構成の計画を作ることをいいます。IPOに向けた資本政策については以下の記事で詳しく解説を行っていますので、合わせてご覧ください。
⇒【経営者必読】IPOに向けた成功する資本政策|上場後の資金調達の仕組みも解説
⇒資本政策とは?必要性や考慮すべき点、失敗事例まで徹底解説!
直前期になると、さまざまなベンチャーキャピタルからアプローチを受けることがありますが、資金調達の必要性がなければ無理に出資を受け入れる必要はありません。
資本政策を見直すことで、ここまで検討してきた株主比率が変わってしまうことがあります。そのため、既存の株主の反感を買ってしまったり、上場後の株主総会で重要な意思決定に影響が出る可能性など様々な事態が発生します。
ただし、企業によって状況も異なってくるので、ここまで一緒に上場準備をしてきたIPOコンサルタントに相談するのもよいでしょう。
IPOコンサルタントについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒IPOコンサルティングの種類や業務とは?必要なコストや選ぶ際のポイントも徹底解説!
3. 市場を選定する
上場申請に向けてこの時期に上場する市場を決める必要があります。
市場は、東京・名古屋・福岡・札幌の証券取引所ごとに本則市場と新興市場に区分されています。
東京証券取引所
東京証券取引所の市場区分は2022年4月に再編が行われ、「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」となりました。(※以前は市場第一部、市場第二部、マザーズ及びJASDAQ(スタンダード・グロース)の4区分)
| プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 | |
|---|---|---|---|
| 市場の特徴 | 海外投資家と対話可能な大企業向けの市場 | 国内を中心に事業を展開している企業向けの市場 | 高い成長性が期待できるベンチャー・スタートアップ企業向けの市場 |
| 流通株式時価総額 | 100億円以上 | 10億円以上 | 5億円以上 |
| 流通株式比率 | 35%以上 | 25%以上 | 25%以上 |
この市場再編により、各市場区分にそれぞれコンセプトが定められました。「プライム市場」「スタンダード市場」「グロース市場」の各コンセプトは以下になります。
プライム市場
多くの機関投資家の投資対象になりうる規模の時価総額(流動性)を持ち、より高いガバナンス水準を備え、投資家との建設的な対話を中心に据えて持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場です。
スタンダード市場
公開された市場における投資対象として一定の時価総額(流動性)を持ち、上場企業としての基本的なガバナンス水準を備えつつ、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にコミットする企業向けの市場です。
グロース市場
高い成長可能性を実現するための事業計画及びその進捗の適時・適切な開示が行われ一定の市場評価が得られる一方、事業実績の観点から相対的にリスクが高い企業向けの市場です。
近年の傾向では、上場する企業はグロース市場を選択する企業が多く見受けられます。
グロース市場・上場市場については、こちらの記事もご参照ください。
⇒グロース市場とは?市場区分の再編による変化を徹底解説!
⇒東京プロマーケットとは?上場企業一覧・上場市場の選び方・メリット・デメリットについて解説
東京証券取引所以外の証券取引所
東京証券取引所の他にベンチャー企業向けの他の市場として、
・名証ネクスト市場(旧: 名証セントレックス)
・札証アンビシャス
・福証Q-Board
があります。
| 名証ネクスト市場 | 札証アンビシャス | 福証Q-Board | |
|---|---|---|---|
| 市場の特徴 | ・将来のステップアップを見据えた事業計画及び進捗の適時・適切な開示が行われ、一定の市場評価を得ながら成長を目指す企業向けの市場 | ・北海道に関連のある企業 ・近い将来における本則市場へのステップアップを視野に入れた中小・中堅企業向けの育成市場 |
・九州周辺に本店を有する企業または九州周辺における事業実績・計画を有する企業 ・新しい技術またはユニークな発想などにより今後の成長の可能性がある企業 |
| 流通株式時価総額 | 基準なし | 基準なし | 基準なし |
| 流通株式比率 | 基準なし | 基準なし | 基準なし |
ネクスト市場
ネクスト市場は名古屋証券取引所における市場区分の一つになります。名古屋証券取引所は、全国のIPO準備企業に門戸を開き、近い将来の上位市場へのステップアップが期待される次世代の企業向けにネクスト市場が開設されています。
ネクスト市場のコンセプトは以下のように定められています。
事業実績の観点からリスクを有するものの、将来のプレミア市場又はメイン市場への市場区分の変更を見据えた事業計画及びその進捗の適時・適切な開示が行われ、一定の市場評価を得ながら成長を目指す企業向けの市場
アンビシャス市場
札幌証券取引所のアンビシャス市場は、「近い将来における本則市場へのステップアップを視野に入れた中小・中堅企業向けの育成市場」というコンセプトがあります。
対象企業は以下のようになっています。
・成長が見込まれる中小企業
・安定的な成長を続けている中小・中堅企業
・北海道と何らかのつながりを有している企業
福証Q-Board
福岡証券取引所のQ-Boardは、地域経済の発展に寄与するために、成長の可能性を有する企業に対してより早い段階から証券市場を通じた資金調達の機会を提供することにより、新規産業の育成を支援するととともに、投資者に対し幅広い投資機会を提供することを目的に創設された市場になります。
そのため、Q-Boardの上場対象企業は株式公開を志向する企業化の初期段階にある企業を含め、成長の 可能性を有する企業になっています。
それぞれの市場の特徴を比べた上で、自社にあった市場を選択するようにしましょう。
4. 申請書類を作成する
上場申請の際には多くの申請書類が必要になります。そのため、申請期に用意しようと思っても申請に間に合わない可能性があるため、直前期から書類の作成に取り掛かるべきでしょう。
上場審査を受ける企業の信頼性の証明となる、これまでの内部監査や様々な管理体制のもと作成されるようになったレポートなど必要な書類が数多くあります。
上場申請の際に必要な申請書類の詳細は以下の東京証券取引所のページに記載がありますので合わせてご覧いただければと思います。
参考:提出書類フォーマット
さらに、この申請書類は印刷会社を通して印刷および製本されたものを提出する必要があるので、スケジュールには余裕を持たせることをお勧めします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、IPO準備のスケジュールのうち、申請を行う1期前の直前期に行うことについて解説を行いました。IPO準備は、長期間を要し、作業も多岐にわたります。特に申請の1期前である直前期は、上場審査を通過できるようにするために、経営管理体制の運用や改善を行ったりする大切な期間になります。
IPOを成功させるためには、IPOに向けたスケジュールをしっかりと把握し、計画的にIPO準備に取り掛かることが大切になります。まずは、ショートレビューを受けて、自社の問題点の解消から始めましょう。
スタートアップ・ベンチャーの経営をされている方にとって、事業に取り組みつつ資金調達や資本政策、IPO準備も進めることは困難ではないでしょうか。
財務戦略の策定から実行まで担えるような人材をを採用したくても、実績・経験がある人を見つけるのには非常に苦労するといったこともあるでしょう。
このような問題を解決するために、SOICOでは「シェアリングCFO®︎」というCFOプロ人材と企業のマッチングサービスを提供しています。
シェアリングCFO®︎では、経験豊富なCFOのプロ人材に週1日から必要な分だけ業務を依頼することが可能です。
例えば、ベンチャー企業にて資金調達の経験を持つCFOに、スポットで業務を委託することもできます。
専門的で対応工数のかかるファイナンス業務はプロの人材に任せることで、経営者の方が事業の成長に集中できるようになります。
「シェアリングCFO®︎」について無料相談を実施しているので、ご興味をお持ちの方はぜひ下のカレンダーから相談会の予約をしてみてくださいね!
この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。