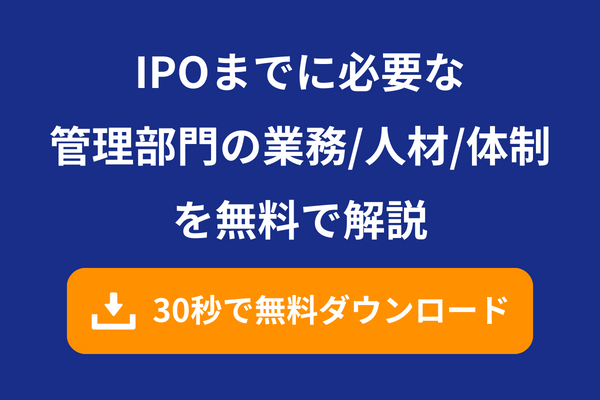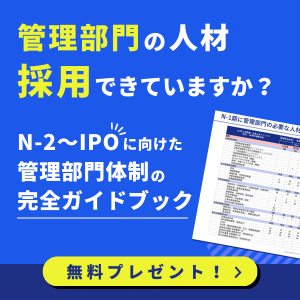COLUMN
コラム
東京プロマーケットへの上場は意味がない?市場の特徴とTPMに上場する意義を解説
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)
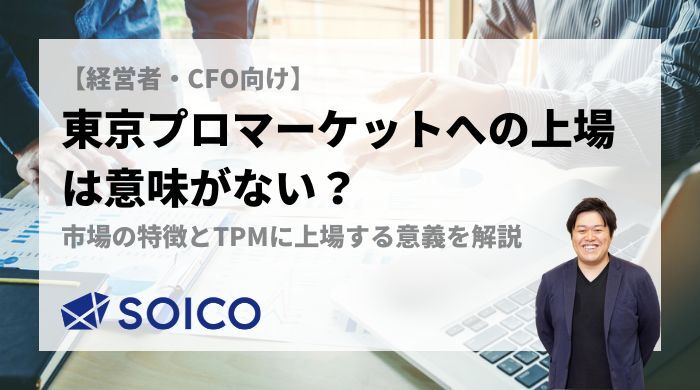

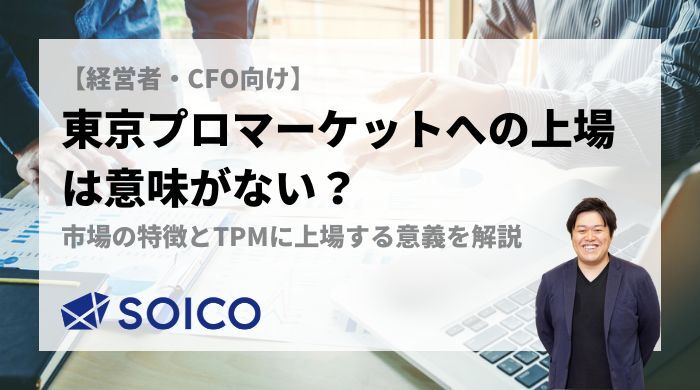
『資金調達の手引き』
調達ノウハウを徹底解説
資金調達を進めたい経営者の方の
よくある疑問を解決します!

2022年4月に行われた東京証券取引所の市場再編により、グロース市場・スタンダード市場・プライム市場へと再編され、上場するために必要な要件が厳密に定められました。
そのため、企業の経営者の中には上場をしたいけれども、上場するために必要な要件を満たすのが難しいため、上場するのは厳しいと諦めてしまっている方もいると思います。
東京証券取引所には、一般市場とは別に東京プロマーケットと呼ばれる新興の株式市場が存在します。
この東京プロマーケットは、近年上場企業も増加しており注目を集めている一方で、東京プロマーケットに上場するのは意味が無いと言われることもあります。
そこで本記事では、東京プロマーケットの特徴や東京プロマーケットに注目が集まる理由、そして東京プロマーケットに上場する意義について詳しく解説を行っていきます。
グロース市場については、こちらの記事もご参照ください。
⇒グロース市場とは?市場区分の再編による変化を徹底解説!
目次
東京プロマーケットとは

東京プロマーケットとは、2009年に解説された東京証券取引所が運営する株式市場の1つで、「TPM」や「プロマーケット」とも呼ばれています。また、東京プロマーケットは、一般市場(グロース市場・スタンダード市場・プライム市場)に続く新興の株式市場として近年注目されてきています。
一般市場へ上場を行うためには売上や利益の額、株主数、流通株式といった形式基準を満たす必要がありますが、東京プロマーケットは形式基準がないので一般市場に比べて上場しやすいという特徴があります。
東京プロマーケットについては以下の記事でも詳しく解説を行っていますので合わせてご覧くださ
⇒【経営者必読】東京プロマーケットとは?上場市場の選び方について解説
東京プロマーケットの特徴
-300x200.png)
東京プロマーケットには以下のような特徴があります。
・ 上場までの準備期間が短い
・市場の参加者はプロの投資家に限られる
・ オーナーの持株比率を維持できる
・J-Adviserによる上場支援が受けられる
以下これらの特徴について詳しく解説を行っていきます。
上場までの準備期間が短い
東京プロマーケットは上場までの準備期間が短いという特徴があります。
グロース市場やプライム市場などの株式市場に上場する場合、監査法人の監査証明が2期分必要となるなど、 上場の準備に少なくとも3年はかかります。 しかし、東京プロマーケットは上場申請に必要な監査期間は1年であるため、他の市場と比べ早く上場することができ、 約2年程で上場を行うことが可能です。さらに、審査の期間が短いため、上場準備にかかるコストの削減をすることができるという特徴があります。
一般的なIPOの準備期間のスケジュールについては以下の記事で詳しく解説を行っていますので合わせてご覧ください。
⇒IPOの準備スケジュール|直前前々期から申請期まで解説
⇒上場スケジュール:直前期|直前期(N-1期)の過程について解説
⇒上場スケジュール:申請期|申請期の過程について解説
市場の参加者はプロの投資家に限られる
東京プロマーケットの最大の特徴は市場の参加者がプロの投資家に限られていることです。
東京プロマーケットに上場している企業は、成長性はあるけれども、実績が十分ではないベンチャー企業が多く、業績や株価の変動が大きく、その分、投資家のリスクが大きくなります。そのため、市場参加者はある程度リスクを許容できるプロの投資家に限られています。
オーナーの持株比率を維持できる
東京プロマーケットでは流動させなければならない株式数や株式比率に関する基準がありません。また、上場時に株式を手放す必要がないため、株主構成を上場時に見直す必要がなく、オーナーの持株比率を維持したまま上場を行うことができます。それによって、経営の支配権を維持したまま上場をすることが可能であるという特徴があります。
資本政策については、こちらの記事もご参照ください。
⇒資本政策とは?必要性や考慮すべき点、失敗事例まで徹底解説!
⇒【経営者必読】IPOに向けた成功する資本政策|上場後の資金調達の仕組みも解説
J-Adviserによる上場支援が受けられる
東京プロマーケットでは、J-Adviserと呼ばれる東京証券取引所から認証を受けたアドバイザーによるアドバイスを受けることができるという特徴があります。 J-Adviser は東京プロマーケットに上場を行う企業の審査の実施や、情報開示やファイナンスに関する各種手続きなどを行っています。
このように東京プロマーケットへの上場を行う際には専門家による手厚いサポートを受けることができるという特徴があります。
東京プロマーケットへの上場に意味が無いと言われる理由

東京プロマーケットへの上場は意味が無いと言われるのは主に以下の2つの理由が挙げられます。
・資金の流動性が低い
・資金調達がしにくい
これらについて詳しく解説をしていきます。
資金の流動性が低い
東京プロマーケットの特徴として、市場の参加者がプロの投資家に限られているということを解説しました。
一般の投資家に比べて、プロの投資家は全体の人数が少ないため株式の売買の数が少ないことに加えて、プロの投資家は短期的なキャピタルゲインを目的としておらず、積極的な売買がなされることが無いため、市場の流動性が低くなります。
しかし、市場の流動性が低いということは、裏返すと日々の株価の変動の影響を受けることなく安定した経営を行うことができるとも考えることができます。 そのため、長期的な視点で経営をすることができるというメリットがあるでしょう。
資金調達がしにくい
東京プロマーケットは新規上場時の資金調達がしにくいというデメリットがあります。
一般的には、株式市場に上場した際に、株式の新規公開時での株式の売り出しによって、資金調達を行うことができるというメリットがあります。しかし、東京プロマーケットは市場参加者がプロ投資家に限られていることで、市場の流動性が低いため、この新規公開時の売り出しで資金調達を行うのが難しくなっています。
資金調達については、こちらの記事もご参照ください。
⇒資金調達の手段・方法には何がある?それぞれのメリット・デメリットも徹底解説!
⇒ベンチャー・スタートアップの資金調達方法とは?投資ラウンド別・調達事例を含めて徹底解説!
⇒返済不要な資金調達とは?メリットやデメリット、調達時の注意点を徹底解説!
⇒資金調達コンサルティングサービスとは?選び方や注意点まで徹底解説!
東京プロマーケットに注目が集まる理由とは
上述のように東京プロマーケットへの上場は意味がないと言われることがありますが、近年、東京プロマーケットに注目が集まっています。
東京プロマーケットの上場企業数は2009年の開設以来右肩上がりで上昇しており、2022年には21社が東京プロマーケットへの上場を果たしました。今後も上場企業数の増加が見込まれており、東京プロマーケットが注目されています。
東京プロマーケットに注目が集まる背景として、 2022年4月に行われた東京証券取引所の市場再編が挙げられます。この市場再編により、今までの東証一部、東証二部、JASDAQ、マザーズという市場区分は、グロース市場、スタンダード市場、プライム市場という新しい区分に再編されました。
この市場再編により今まで曖昧だった上場基準が明確に定められました。それによって、上場時点の基準を維持できないと上場廃止となるため、一般市場への上場は以前より厳しくなりました。
そこで、株主数や流通株式、時価総額や利益の額といった形式基準がない東京プロマーケットが新しい上場先として注目されるようになりました。
東京プロマーケットに上場する3つの意義

東京プロマーケットに上場をすることによって、企業は次のようなメリット・意義を得ることができます。
・東証上場企業としてのメリットが得られる
・他市場へのステップアップに活用できる
・組織体制が強化される
これらのメリットについて詳しく解説をしていきます。
東証上場企業としてのメリットが得られる
東京プロマーケットに上場することで、東証上場企業としてのメリットを得ることができます。
東証上場企業としてのメリットとして、
・企業の信用力・知名度の向上
・従業員の士気の向上
などがあります。
東京プロマーケットは東証の他の市場と比べて上場基準が低く、上場へのハードルが低いですが、東京プロマーケットへ上場すればその企業は「東証上場企業」となることができます。
このように、上場のハードルが低いにも関わらず、上場企業としてのメリットを受けることができるという点で、東京プロマーケットに上場する意義があると言えます。
他市場へのステップアップに活用できる
東京プロマーケットから他市場へのステップアップに活用できるという意義があります。
グロース市場やスタンダード市場への上場を目指しているものの何年も上場できないという企業は多く存在しています。そこで、上場基準が厳しいグロース市場やスタンダード市場を目指すのではなく、上場基準が無く比較的上場しやすい東京プロマーケットへ上場することで、上場企業としてのメリットを受けながら、企業の成長を加速することができます。
そして、東京プロマーケットに上場することで企業を成長させ、グロース市場やスタンダード市場の上場基準を満たした後に一般市場へ市場変更するといった活用をすることができます。
組織体制が強化される
東京プロマーケット上場を行う過程で、企業の組織体制が強化されるという意義があります。
東京プロマーケットへの上場を行う中で、コーポレートガバナンスと内部管理体制の整備と適切に機能しているかということが求められます。そのため、経理や財務、労務管理といった管理体制を強化することができます。企業としての基盤を築いていくことで組織経営体制が確立されていきます。そうすることで、効率性が向上し、組織全体の生産性を高めていくことが期待できます。
コーポレートがバンスについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒コーポレートガバナンス(企業統治)とは?目的・強化方法・歴史的背景について解説!
⇒コーポレートガバナンス・コードの5つの基本原則|特徴・制定の背景・適用範囲と拘束力について解説
⇒コーポレートガバナンス・コードとは?概要・特徴・制定された背景について解説
⇒【2021年改訂】コーポレートガバナンス・コードの実務対応と開示事例
まとめ
いかがだったでしょうか。
本記事では、新興上場市場の東京プロマーケットへの上場する意義について解説をしました。
上場基準が厳しいグロース市場・スタンダード市場をいきなり目指すのでは無く、まずは東京プロマーケットに上場し、上場企業としてのメリットを享受することで、一般市場へのステップアップを行うことで企業価値を高めていくという戦略も存在します。
企業の上場は外部からの信頼性と魅力を高めることにも寄与するので、優秀な人材を集めるための手段、取引先や金融機関との関係性の強化など、企業体制の強化にもつながります。
本記事が上場を目指しているスタートアップ・ベンチャー企業の経営者の方の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
また、管理部門体制の構築をしたり、CFO人材の採用を進めたり、資金調達を加速させたりするには、プロの専門家に相談するのが一番です。
そこでSOICOでは、CFO中心とした管理部門組織の構築や、ファイナンスに長けたプロによる、個別の無料相談会を実施しております。
・CFOやバックオフィスの部長クラスが採用できている会社は、給与/役員報酬、株式報酬、採用手法は具体的にどうやっているか?
・今の自社の経営状態を踏まえた上で、資金調達を失敗しないために、どういったポイントを意識して進めるべきか?
そんなお悩みを抱える経営者の方に、要望をしっかりヒアリングさせていただき、
適切な情報をお伝えさせていただきます。
ぜひ下のカレンダーから相談会の予約をしてみてくださいね!
この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。