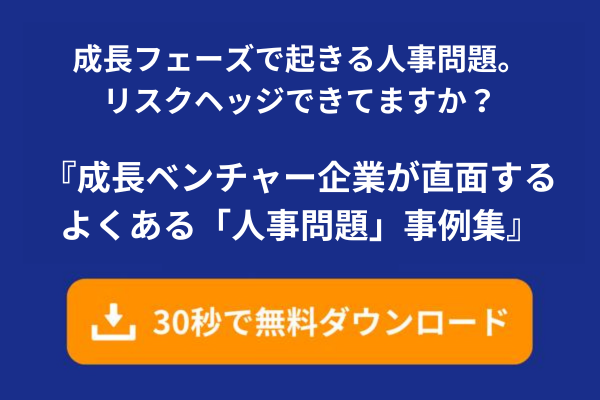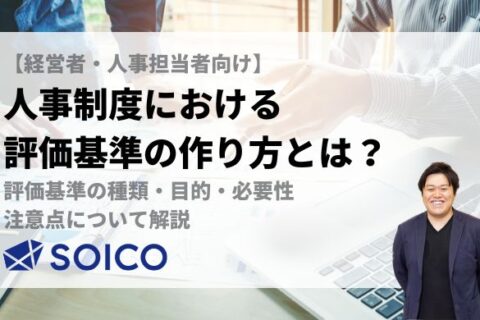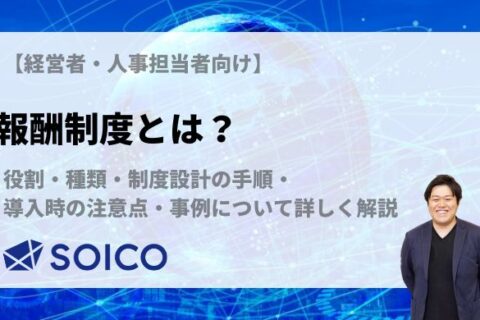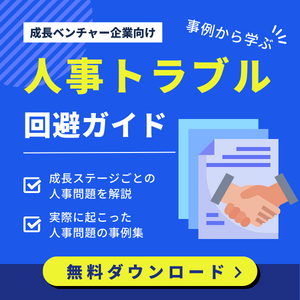COLUMN
コラム
賃金制度とは?年功給・職能給・成果主義賃金制度について詳しく解説
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)

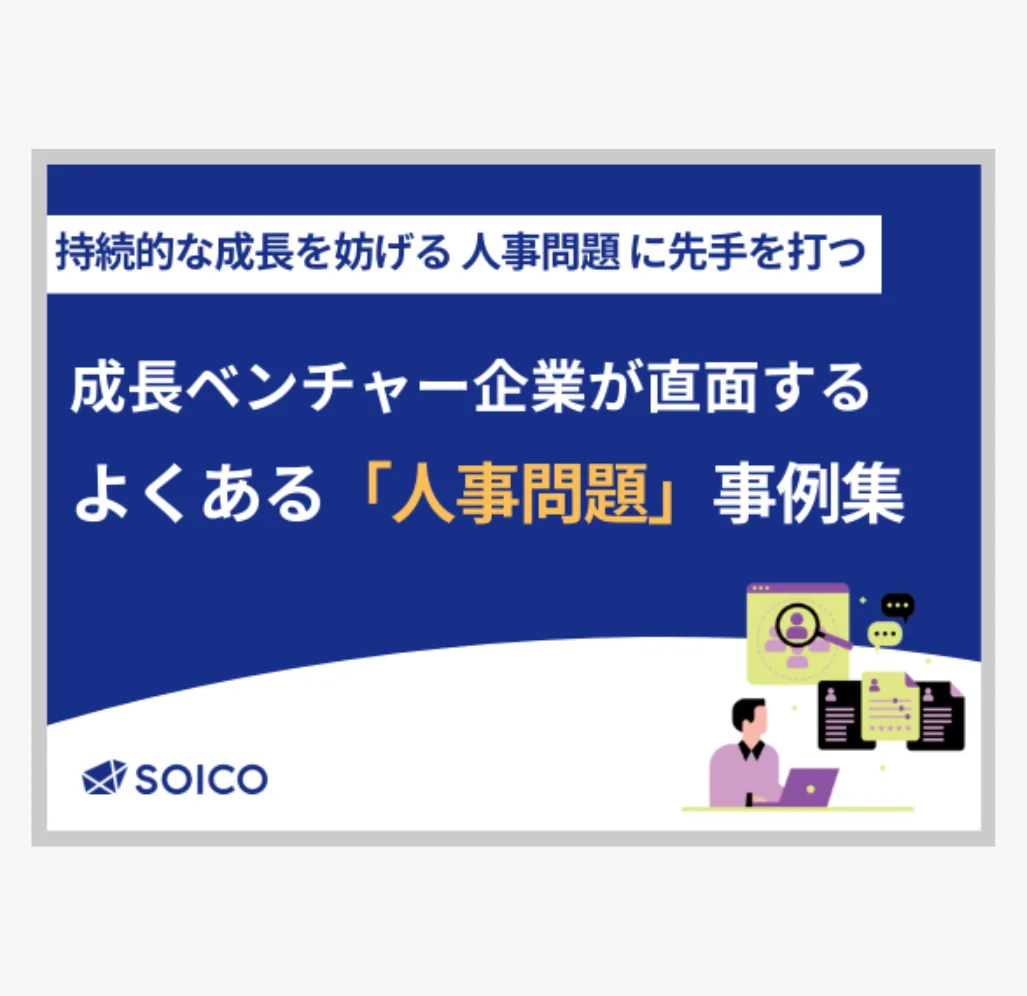

成長ベンチャー企業が直面する
よくある「人事問題」事例集
成長ステージごとにも解説!
今までの日本の企業では年功序列と終身雇用制度が中心でしたが、社会が大きく変化する中で仕事での成果をもとに給与を決めたり、従業員の能力や役割に応じて給与を決めるなど賃金制度にも変化が見え始めています。
かつて、優秀な学生は官僚や大手企業に進むことが一般的でしたが、この近年では官僚に進む優秀層は減少し、外資系企業や裁量のあるミドルベンチャーやメガベンチャーを卒業後の選択肢に入れる就活生が増えているというニュースも目にします。
特に、メガベンチャーでは新卒入社の新入社員の給与を高く設定することで優秀な学生を囲い込んでいる印象を受けます。賃金制度だけでなく、仕事における自身の裁量や未来の独立を見据えてスタートアップ企業をファーストキャリアにする学生も増えているとも聞きます。
そこで本記事では、賃金制度が確立していないスタートアップ企業やこれから規模を大きくする中で賃金制度の見直しを考えているベンチャー企業に向けて賃金制度について解説していきます。
人事制度について、こちらの記事もご参照ください。
⇒人事制度とは?人事制度の目的・設計・歴史・新しい人事制度について徹底解説!
⇒人事制度と設計時の注意点|人事制度の種類と構築の流れについて解説
⇒人事考課制度の作り方|会社と社員へ与える影響と運用の注意点を解説
⇒人事制度設計コンサルティングとは?選び方・費用相場・おすすめ企業も紹介
⇒等級制度とは?3種類の等級制度と作成方法・導入事例について解説
⇒評価制度とは?評価制度の目的・種類・制度の導入時に考えるべきポイントを解説
⇒報酬制度とは?役割・種類・制度設計の手順・導入時の注意点・事例について詳しく解説
賃金制度とは
賃金とは、会社が従業員に対して金銭で支払う報酬全てのことです。賃金には、基本給や諸手当などの月例給与、賞与(ボーナス)、退職金などがあります。また、賃金制度は賃金を従業員に支払う際の根拠となるルールのことです。
賃金には主に以下の5つの体系があり、それぞれ特徴が異なります。
1.年功給
2.能力給
3.役割給
4.職務給
5.成果給
年功給
年功給は、勤続年数や学歴、性別などにより給料が決まっていく制度です。年功給では勤続年数が長ければ、他の人と同じように昇給することができるため、仕事の能力が低い人にとってはメリットが大きい制度です。
高度経済成長期の終身雇用の時代においては年功給は多くの企業で採用されていましたが、終身雇用という採用形態が少なくなってきている現在では年功給ではない企業も増えています。
また、年功給は年齢給や勤続給とも言われます。
年功給のメリット
年功給のメリットは、勤続年数が長くなることで給料が上がっていくため、従業員が会社に長期間従事してくれることです。その結果、会社への帰属意識が高まり、会社にノウハウや技術の知見などが蓄積し、それらの継承や引き継ぎをスムーズに行うことができます。
また、従業員同士の結束力も高まり、チームワークを発揮して仕事に取り組んでくれる期待も高まります。
年功給のデメリット
年功給のデメリットは、人件費が高くなることや、様々なことにチャレンジする人材が少ないことです。
年功給は主に終身雇用制を取り入れいている企業で用いられるため、従業員が高齢化していくと、人件費もその分高騰していき、現状維持で結果を出していなくても給料が上がっていくため、新たなことに挑戦して結果を出そうというモチベーションを与えることが難しくなります。
また、自分より能力が低い人、仕事で結果を出していない人が勤続年数が長いという理由だけで、給料が高いというケースが発生してしまうことで、不公平感を従業員が抱いてしまったり、若い従業員の成長を妨げてしまうというデメリットもあります。
少子高齢化により、ピラミッド型の人口構成が崩れ、また、経済成長も緩やかになり会社の成長も緩やかになった結果、会社が年功給を維持することが難しくなったため、年功給を採用している会社も少なくなってきています。
職能給
職能給は、従業員のレベルをいくつかの等級(グレード)に分け、等級に応じて賃金が決定する制度です。すなわち、学歴や勤続年数ではなく、会社における従業員の成長に応じて賃金が上昇していく制度です。
職能給のメリット
職能給のメリットは、従業員の成長に応じて賃金が上昇していく制度であるため、やる気のある将来有望な従業員の離職を防ぐことができることや、ジョブローテーションによる、従業員の挑戦を後押しすることができ、従業員が様々なことに挑戦しようとする環境や、成長していこうといった従業員の意欲を育むことができることがあります。
また、仕事に紐づいた賃金制度ではないため、ジョブローテーションなどの人事異動をしやすく、人事側にもメリットがあります。
さらに、成長支援による離職抑制効果を期待でき、安定した労使関係を作ることができ、加えて、従業員は賃金に対して納得感を持つことができるといったメリットもあります。
職能給のデメリット
職能給のデメリットは従業員の能力を正しく評価することが難しいことです。レベルに応じて等級を設定しても、従業員の能力を正しく評価できなければ、結果的に年功序列のような制度運用になってしまうという問題が発生します。
また、能力を高め、高い等級に昇格することで、役職につかずとも、役職を持つ人と同等の給料をもらうことができてしまい、結局人件費が高くなってしまうという問題も発生してしまうというデメリットがあります。
職能給という制度自体はとても素晴らしい制度ではありますが、うまく運用するのが非常に難しく、職能給を導入する企業は次第に少なくなってしまいました。
成果主義賃金制度
成果主義賃金制度は、能力や年功に応じて賃金が決まるというこれまでの賃金体系とは異なり、仕事の成果に応じて賃金やボーナスを与える制度です。
成果主義賃金制度のメリット
成果主義賃金制度には、企業側には優秀な人材を確保できることや人件費を削減できるというメリットがあります。
成果主義賃金制度では、仕事の成果に応じた賃金をもらうことができるため、年功序列や職能給などで正当な評価をされずに不満を抱えていた優秀な人材を企業は集めることができます。
また、仕事の成果を出せていない従業員に対しては高額な賃金を支払う必要がなく、成果に応じた賃金を支払えば良いため、無駄な人件費を支払う必要がありません。
さらに、従業員のメリットは公平な評価を受けることができ仕事に対するモチベーションが向上することや、頑張り次第で収入のアップを期待できることなどがあります。
成果主義賃金制度では、仕事の成果という目にみえる成果に対して賃金が支払われるため、評価にブレが起きづらく、賃金に関する不公平感が発生しにくい制度です。
成果主義賃金制度のデメリット
成果主義賃金制度にはデメリットもあります。
営業部などの仕事の成果が数値として現れる部署においては、評価がしやすいですが、成果が数値として現れない部署においては評価基準を定めるのが難しいという問題があります。
また、個人の成果が給料に直結するため、個人の成果をあげることを優先してしまうことでチームワークが悪くなってしまったり、長期的な成果ではなく、短期的な成果をあげようと動く人が増えてしまうなどのデメリットもあります。
賃金制度の構成要素
日本における一般的な賃金制度の構成要素は、毎月支給される基本給に加えて、諸手当、賞与、退職金によって構成されています。以下では、それぞれについて解説を行います。
・基本給
・手当
・賞与
・退職金
基本給
基本給とは、交通費や住宅手当などの諸手当を除いた基本的な給料のことです。大まかに言えば、月単位で支給される固定の賃金を基本給といいます。
基本給には、年齢給や、勤続給、能力給、職務給、成果給、歩合給などの様々な種類があり、業種・職種の特色や、会社ごとの考え方をもとにどの制度をとるかが変わります。昔は年功給と職能給が基本給の中心でしたが、最近では職務給や成果給をとる会社が増えています。
どの給与制度にもメリット・デメリットがあり、一概にどれが良いとは言えず、様々な考え方のもとで柔軟にどの給与制度をとるかを決めることが大切です。
手当
手当とは、基本給とは別に支払われる賃金のことです。法律上は、残業代は必ず支払わなければいけませんが、残業代以外には必ず支給しなければならない手当はありません。手当には、通勤手当、住宅手当、家族手当などの種類があります。また、コロナ禍でテレワークを実施する会社が増えたことでテレワーク手当を支給するなど、時代に合わせた手当を支給する会社も増えています。
手当を充実させることで、離職率を低下させたり、人材の採用を行いやすくなります。一方で、単純に支給項目を無くすことは、不利益変更に当たってしまうため、一度取り入れた手当を廃止することは簡単には行えません。そのため、諸手当を導入する際には、自社に必要があるかどうかを検討し、必要であればどれくらいの水準で手当を支給するかという点を考える必要があります。
賞与
賞与とは企業の業績に応じて従業員に支給する賃金のことをいいます。いわゆる、ボーナスのことです。賞与の金額は企業によって様々な決定方法があります。
例えば、企業の経常利益を基準として賞与の原資を決定し、人事評価に応じて賞与の額を決める方法や、基本給をベースに◯カ月分を支給するという方法もあります。
退職金
退職金は従業員が退職する際に支給する賃金のことです。
退職金の額は昔は、「退職時の基本給 × 在籍年数に応じた係数」によって決められることが多かったですが、近年では、「ポイント制退職金制度」を導入する企業が増え、会社に在籍していた期間における会社への貢献度に応じて退職金を支払う企業が増えています。
退職金は法律で支払わなければならないと定められている訳ではありませんが、退職金制度を導入することで、採用活動を行いやすくなったり、勤続年数が長くなるなどのメリットがあります。
退職金は定年退職の際に支払われるというイメージが強いですが、中途退職や解雇の際、従業員が死亡した場合なども退職金の支給対象になります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
本記事では、賃金制度が確立していないスタートアップ企業やこれから規模を大きくする中で賃金制度の見直しを考えているベンチャー企業に向けて賃金制度について解説してきました。
優秀な人材を採用するため、また優秀な従業員のモチベーションを高めたり、社内でのキャリアを高めてもらうために賃金制度を見直し、企業全体の組織力を高めることにつながれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
人事評価については、こちらの記事もご参照ください。
⇒人事評価とは?人事評価の目的・導入方法・注意点について解説
⇒人事評価シートの記載方法|人事評価シートの目的と職種別評価項目を徹底解説
⇒人事評価制度の作り方|評価を作る際の注意点や成功例についても解説
⇒人事評価の項目とは?項目の種類や評価項目例・参考事例をご紹介!
⇒人事評価の際の目標設定とは?目標設定のメリット・SMARTの法則を解説
⇒人事評価コンサルタント|メリット・デメリット・選ぶ際のポイントについて解説
⇒人事評価面談|面談の目的・進め方・ポイントについて解説
⇒人事評価制度のメリット・デメリット|デメリットの解決策・人事評価制度の失敗例についても解説
新しい人事制度については次の記事もご参照ください。
⇒【2023年最新】トレンドの人事制度|最新人事制度9選を徹底解説
⇒MBO(目標管理制度)とは?具体例と作成時のポイント・OKRとの違いについて解説
⇒OKR(目標と主要な成果)とは?目標の設定方法・運用の際のポイントを丁寧に解説
⇒360度評価とは?評価制度の特徴・メリット・デメリット・導入の際のポイントなどを解説
⇒バリュー評価とは?評価制度の仕組みや特徴・メリットや注意点・導入事例まで解説
⇒ミッショングレード制とは?他の制度との関係・制度の導入に必要な役割定義書の作成方法まで詳しく解説
⇒コンピテンシー評価とは | メリット・デメリットや導入時の注意点をご紹介!
⇒ノーレイティングとは?メリット・デメリット・評価制度を成功させるポイントを解説
⇒ピアボーナスとは?導入のメリットやデメリット、具体的なツールを徹底解説!
よくある「人事問題」事例集
・成長ステージごとに起きやすい人事問題の種類
・実際にベンチャー企業で起こった人事問題の事例
これら「ベンチャーの人事問題」について資料にまとめました。
- <主な内容>
- ●ベンチャー企業が人事問題に先手を打つべき理由
- ●人事問題が表面化しやすい時期とは?
- ●成長ステージ別 よく見られる人事問題
- ●事例1:上司の評価能力不足と曖昧な評価基準による問題
- ●事例2:単一的なキャリアパスによる問題
- ●事例3:優秀な幹部人材の社外流失についての問題
フォームに必要事項をご記入いただくと、
無料で資料ダウンロードが可能です。
この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。