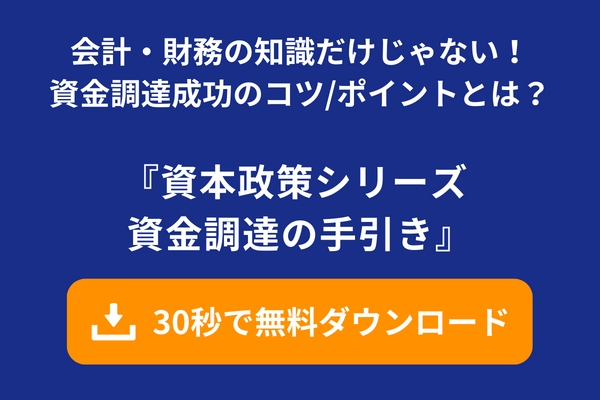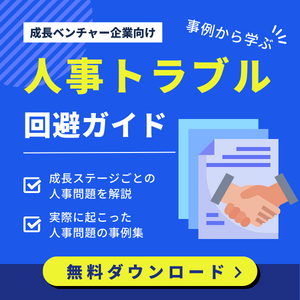COLUMN
コラム
ピアボーナス制度の6つの失敗例|制度の導入事例と成功させるためのポイントも解説
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)
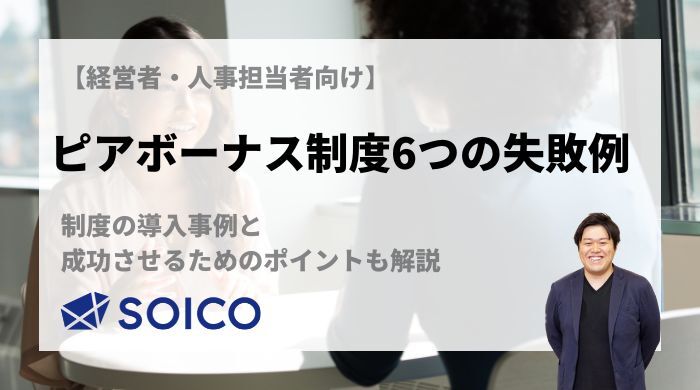

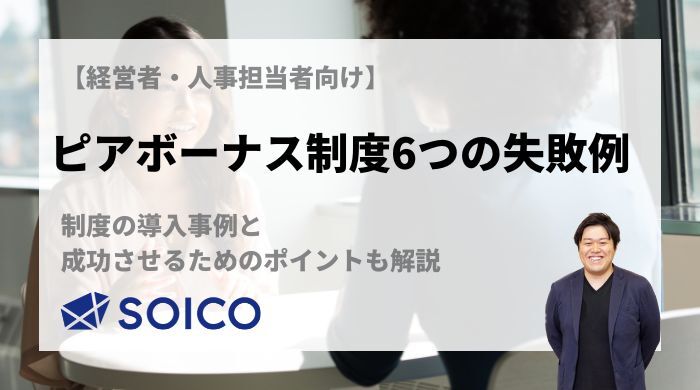
『資金調達の手引き』
調達ノウハウを徹底解説
資金調達を進めたい経営者の方の
よくある疑問を解決します!
社員同士で報酬を送り合うことによって、社内のコミュニケーション向上や満足度向上に繋げる制度が「ピアボーナス」です。
ピアボーナスを導入することによってさまざまなメリットがありますが、その反面で失敗している企業が多いのも事実です。
本記事では、ピアボーナスが失敗する事例はどのようなものか、成功させるポイントは何かを実際にピアボーナスを導入している企業の事例とともに詳しく解説していきます。
失敗例から成功するポイントを解説していきますので、「ピアボーナスの導入を検討している」方や、「ピアボーナスの導入がうまくいっていない」方はぜひ最後までご覧ください。
人事評価・評価制度については、こちらの記事もご参照ください。
⇒評価制度とは?評価制度の目的・種類・制度の導入時に考えるべきポイントを解説
⇒人事評価とは?人事評価の目的・導入方法・注意点について解説
⇒人事評価シートの記載方法|人事評価シートの目的と職種別評価項目を徹底解説
⇒人事評価制度の作り方|評価を作る際の注意点や成功例についても解説
⇒人事評価の際の目標設定とは?目標設定のメリット・SMARTの法則を解説
⇒人事評価コンサルタント|メリット・デメリット・選ぶ際のポイントについて解説
⇒人事評価面談|面談の目的・進め方・ポイントについて解説
⇒人事評価制度のメリット・デメリット|デメリットの解決策・人事評価制度の失敗例についても解説
⇒人事評価の成功事例10選!人事評価項目の種類・人事評価制度の成功事例を幅広くご紹介!
目次
ピアボーナスとは
ピアボーナスとは企業が従業員へ報酬を支払うボーナス制度とは異なり、従業員同士が報酬やギフトなどを送り合う仕組みです。専用のスマホアプリや社内のチャットツールを使用して、高評価や感謝を送りたい相手にメッセージやポイントを送信します。
社内で評価内容を公表したり、送られて貯まったポイントを現金や商品などに換算する仕組みです。ピアボーナスにおける評価の対象は、仕事の成果ではなく「社内の助け合い」に対して送られるのが一般的です。
そのため、会社や上司が従業員や部下の成果などを一方的に評価する目的で行われるのではなく、従業員同士の協調性や従業員のエンゲージメント向上を目的として導入されることが多くなっています。
ピアボーナスについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒ピアボーナスとは?導入のメリットやデメリット、具体的なツールを徹底解説!
ピアボーナス導入事例
ピアボーナスを導入している企業の事例を詳しく見ていきましょう。
実際にピアボーナスを導入している企業としては次の5社が有名です。
・株式会社メルカリ
・株式会社日阪製作所
・損害保険ジャパン株式会社
・イグナイトアイ株式会社
・株式会社ヴィクセス
それぞれの企業が実際にどのようにピアボーナス制度を導入しているのか、詳しく見ていきましょう。
株式会社メルカリ
メルカリは「メルチップ」というピアボーナスを従業員同士で送り合う制度を導入しています。
わざわざアプリなどを使用するのではなく、使用しているSlack上で送り合うことができるので、従業員の活発な利用を促すことができます。
導入した結果、従業員のエンゲージメントが向上しただけでなく、愛社精神の向上やマネージャーのフィードバックの向上などにも効果を発揮しました。
株式会社日阪製作所
日阪製作所は2018年に「働きがい支援室」を立ち上げ、社員の働きがい向上のためのさまざまな施策を実施しました。その一環としてピアボーナス制度を導入しています。
日阪製作所の社風は真面目で柔軟性に乏しく、自分の仕事にやりがいや意義を感じる従業員が少ないという課題がありました。
そこで、ピアボーナス制度を導入したことによって、従業員同士が感謝を伝え合うようになり、これまではあまり社内で日が当たらなかった人事や営業の従業員のエンゲージメントも向上するなどの成果を出すことができました。
損害保険ジャパン株式会社
損保ジャパンは事故にあった顧客の事故対応を行う「保険金サービス部門」でピアボーナスを導入しています。
この部門においては従業員同士のコミュニケーションが非常に重要になるので、これまでもアナログでのサンクスカードを利用するなどして従業員同士の感謝を伝え合う環境を重視していました。
しかしアナログであるがゆえに、対応が一過性のものとなってしまい、継続的に運用されないという点が課題でした。
そこで、ピアボーナスツールを導入し、従業員はLINEのスタンプを送るような感覚で感謝を伝え合うことができるようになり、それだけでなく案件の共有なども容易にできるようになっています。
イグナイトアイ株式会社
採用管理システムを提供するイグナイトアイは、2018年9月という比較的早い時期からSlackのアプリ「HeyTaco!」を利用してピアボーナス制度を導入しています。
業務拡大に伴い、従業員の採用が増えた同社は、ミッション達成のためには社員同士の質の高いコミュニケーションが必要だと判断します。
そこで、ピアボーナス制度を導入し、多くの感謝(タコス)を受け取った社員と、多くの感謝(タコス)を送っている社員も定期的に表彰を行っています。
また、感謝(タコス)は商品と交換することができるので、社内のコミュニケーションだけでなく従業員のエンゲージメントも向上します。
株式会社ヴィクセス
飲食店を経営するヴィクセスは、アルバイト従業員の活躍や主体的な仕事への取り組みを重視しています。
アルバイト従業員にも高いモチベーションで働いてもらえる環境を作るための施策の一環としてピアボーナス制度を導入しました。
ピアボーナスを送ったり、もらったりした数に応じて社内表彰する仕組みを導入しており、これによって従業員の満足度が向上し、研修参加率の向上や離職率の低下などの成果をあげることができました。
ピアボーナスが失敗する6つの事例
ピアボーナスが失敗するよくあるケースとして、次の6つの事例をあげることができます。
・お金がかかりすぎる
・導入に手間がかかる
・従業員が正しい使い方をしない
・従業員の人間関係がむしろ悪化した
・ツールが会社にマッチしなかった
・仕事自体に悪い影響を与えてしまった
コスト面、手間がかかる点、また導入をしたことによって人間関係が悪化するようなケースもあります。
ピアボーナスが失敗してしまう事例について詳しく解説していきます。
お金がかかりすぎる
ピアボーナスを導入すると、一定の金銭的なコストが生じます。
ピアボーナスツールを導入する場合には利用料金が発生しますし、ボーナスを商品などに交換する場合にはその費用も会社が負担しなければなりません。
これらの費用は通常の人件費とは別に発生するので、導入によって人件費関連のコストがさらに高くなり、会社によっては「金銭的に継続することが難しい」という状況に陥ってしまう可能性があります。
導入に手間がかかる
ピアボーナス制度が失敗に終わるケースとして、導入したものの、運用に手間がかかるというケースです。
例えば、アナログのサンクスカードなどに手書きで感謝を伝え合うピアボーナス制度を運用する場合、カードに手書きでメッセージを書くというのは従業員にとってかなりの手間となってしまいます。
そのため、制度そのものが従業員にとって手間になり、会社に定着せずに失敗に終わってしまうというケースです。
ピアボーナス制度は感謝を伝える側にとっても、受け取る側にとっても手間がかからないものである必要があるでしょう。
従業員が正しい使い方をしない
従業員がピアボーナス制度の正しい使い方をしないような場合も失敗に終わる可能性があります。
例えば、「ピアボーナスを受け取りやすい業務ばかりを優先する」「従業員が結託してボーナスを送りあい、無駄にボーナスが消費される」「本業に集中しない」といったケースです。
ピアボーナスは通常の人事評価とは別に行われるのが基本ですので、あくまでもピアボーナスは本業よりも後順位となるものです。
にもかかわらず、本業よりもボーナスをもらうことが優先になるような使い方をされて、本業に支障が出るケースも失敗するパターンだと言えます。
従業員の人間関係がむしろ悪化した
ピアボーナス導入によって従業員の人間関係が悪化してしまうケースも失敗の典型例です。
従業員が従業員を評価した言葉というのは社内で共有されるのが一般的です。
そのため「こんなことを言ったら嫌われるのではないか」「なぜこの人は自分ではなく他の人に感謝を伝えるのだろう。私も同じ仕事をしているのに」など、心理的な不満や不安が募って、疑心暗鬼になってしまうケースも珍しくありません。
結果として、会社に言いたいことを言いたくても言えない空気が流れて、むしろ社内の人間関係が悪化してしまう可能性があります。
従来も社内のコミュニケーションが活発ではない企業が突然ピアボーナスを導入すると、このような問題が生じる可能性があるので注意しましょう。
ツールが会社にマッチしなかった
ツールが会社にマッチしないケースもあります。ピアボーナスツールはいくつかありますが、基本的にはスマホやPCなどのオンラインツールを使用するのが一般的です。
しかし、日常的にスマホやPCなどを使用しない会社の場合には、ピアボーナスを利用するためだけにスマホアプリを開いたり、普段はWEBにほとんど接することがないような人も、ピアボーナスのためにWEBにアクセスしなければならなくなります。
このように、そもそも会社の働き方にツールがあっていない場合には、ピアボーナス制度の存在そのものが従業員の負担になる可能性があります。
ピアボーナス制度を導入する際には「自社の従業員にとって無理なく使いこなせるものか」という点をしっかりと確認するようにしてください。
仕事自体に悪い影響を与えてしまった
ピアボーナス制度が本業に悪影響を及ぼしてしまったケースです。
「ボーナスをもらえる仕事ばかり優先する」「ピアボーナスをもらうこと、送ることばかりに気が散ってしまい本業に集中できない」このように、ピアボーナス制度があることによって本業が疎かになってしまう従業員は少なくありません。
ピアボーナス制度はあくまでも本業に付随するものですので、本業に支障が出ないように運用を工夫しましょう。
ピアボーナスを成功させるポイント
ピアボーナスを成功させるためには次の5つの点を踏まえて運用していくことが重要です。
・ピアボーナス推進専門のチームをつくる
・マネージャーや役職者が積極的に参加する
・イベントと絡めてピアボーナスを運用する
・良い投稿を社内で広げる
・会社に合ったピアボーナスシステムを採用する
会社が積極的にピアボーナスを推進すること、また社員が主体的にピアボーナス制度に参加できる取り組みを行うことが重要です。
ピアボーナスを成功させるための5つのポイントについて詳しく解説していきます。
ピアボーナス推進専門のチームをつくる
ピアボーナスを推進するための専門チームを作りましょう。
多くの企業で一般化しつつあるピアボーナス制度ですが、導入していない企業の従業員にとってはまだまだ馴染みの薄いものであることは間違いありません。
そのような企業において、突然ピアボーナス制度を導入したとしても、従業員は遠慮して、積極的に感謝を伝えることはしない傾向にあります。
そのため、推進専門チームのメンバーが積極的に感謝を発信して、従業員が気兼ねなく利用できる環境を整えるようにしてください。
マネージャーや役職者が積極的に参加する
マネージャーや役職者が積極的にピアボーナス制度に参加しましょう。
管理職が部下の頑張りや協力を評価することによって「上司はしっかりと自分を見てくれている」と部下の満足度は高まり、ピアボーナスに対して好印象を持つようになります。
また、上司が参加している場所で同僚が従業員を褒める投稿をすれば、上司の目に見えなかった従業員の頑張りが上司に見えるようになります。
ピアボーナスを活発に運用し、従業員のモチベーション向上に繋げるためには上司の参加が欠かせません。
イベントと絡めてピアボーナスを運用する
イベントと絡めてピアボーナスを運用するなど、運用方法について工夫するようにしましょう。
例えば、新入社員に対して「入社記念ピアボーナス」などを送ることで、新入社員の満足度とピアボーナスに対する気持ちが向上します。
この他、従業員の誕生日、部署のノルマ達成時などにピアボーナスを送るなどのイベントを企画することで、社内で自然にピアボーナスが広がっていくようになるでしょう。
良い投稿を社内で広げる
良い投稿があったら、その内容を会議や社内報などで取り上げて意図的に広げるようにしましょう。
良い投稿が広がることによって、投稿した側もされた側も満足度がさらに高くなります。
また、他の従業員にとっても「自分も広げてもらいたい」という感情が働くので、社内で積極的にピアボーナスが利用されるきっかけになります。
良い投稿は水平的に社内で広げていくように心がけましょう。
会社に合ったピアボーナスシステムを採用する
ピアボーナスのシステムはいくつもありますが、会社に合ったピアボーナスシステムを使用するようにしてください。
特に料金面は非常に重要です。従業員が活発にピアボーナスを送り合うのは、制度としては以上に良いことですが、送れば送るだけ会社の金銭的な負担は大きくなります。
そのため、あらかじめ予算を決めて、予算の範囲内である程度活発に運用できるピアボーナスシステムを採用するようにしてください。
まとめ
ピアボーナスは従業員が従業員に感謝を伝え合う仕組みで、感謝とともにポイントなどを送ることで、貯まったポイントを景品などに交換できます。
従業員の満足度向上と社内のコミュニケーション強化などの効果が期待できます。
しかし、金銭的な負担が大きく、従業員が使い方を間違えてしまうことも多いため、導入したことが失敗に終わってしまう企業も存在します。
適切に運用していくために、会社や上司も積極的に運用に加わるとともに、予算の範囲内で無理なく利用できるシステムの導入などを検討しましょう。
本記事が、ベンチャー・スタートアップ企業の経営者・人事担当者の方のご参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
人事制度について、こちらの記事もご参照ください。
⇒人事制度とは?人事制度の目的・設計・歴史・新しい人事制度について徹底解説!
⇒人事制度と設計時の注意点|人事制度の種類と構築の流れについて解説
⇒人事考課制度の作り方|会社と社員へ与える影響と運用の注意点を解説
⇒人事制度設計コンサルティングとは?選び方・費用相場・おすすめ企業も紹介
⇒等級制度とは?3種類の等級制度と作成方法・導入事例について解説
⇒評価制度とは?評価制度の目的・種類・制度の導入時に考えるべきポイントを解説
⇒報酬制度とは?役割・種類・制度設計の手順・導入時の注意点・事例について詳しく解説
新しい人事制度については次の記事もご参照ください。
⇒【2023年最新】トレンドの人事制度|最新人事制度9選を徹底解説
⇒MBO(目標管理制度)とは?具体例と作成時のポイント・OKRとの違いについて解説
⇒OKR(目標と主要な成果)とは?目標の設定方法・運用の際のポイントを丁寧に解説
⇒360度評価とは?評価制度の特徴・メリット・デメリット・導入の際のポイントなどを解説
⇒バリュー評価とは?評価制度の仕組みや特徴・メリットや注意点・導入事例まで解説
⇒ミッショングレード制とは?他の制度との関係・制度の導入に必要な役割定義書の作成方法まで詳しく解説
⇒コンピテンシー評価とは | メリット・デメリットや導入時の注意点をご紹介!
⇒ノーレイティングとは?メリット・デメリット・評価制度を成功させるポイントを解説
⇒ピアボーナスとは?導入のメリットやデメリット、具体的なツールを徹底解説!
スタートアップ・ベンチャーの経営をされている方にとって、事業に取り組みつつ資金調達や資本政策、IPO準備も進めることは困難ではないでしょうか。
財務戦略の策定から実行まで担えるような人材をを採用したくても、実績・経験がある人を見つけるのには非常に苦労するといったこともあるでしょう。
このような問題を解決するために、SOICOでは「シェアリングCFO®︎」というCFOプロ人材と企業のマッチングサービスを提供しています。
シェアリングCFO®︎では、経験豊富なCFOのプロ人材に週1日から必要な分だけ業務を依頼することが可能です。
例えば、ベンチャー企業にて資金調達の経験を持つCFOに、スポットで業務を委託することもできます。
専門的で対応工数のかかるファイナンス業務はプロの人材に任せることで、経営者の方が事業の成長に集中できるようになります。
「シェアリングCFO®︎」について無料相談を実施しているので、ご興味をお持ちの方はぜひ下のカレンダーから相談会の予約をしてみてくださいね!
この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。