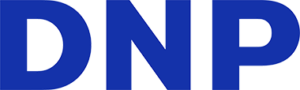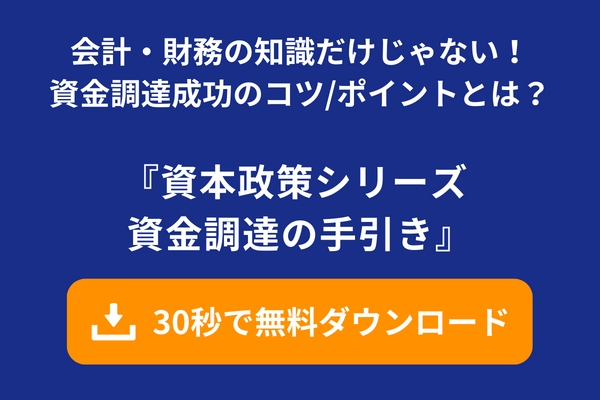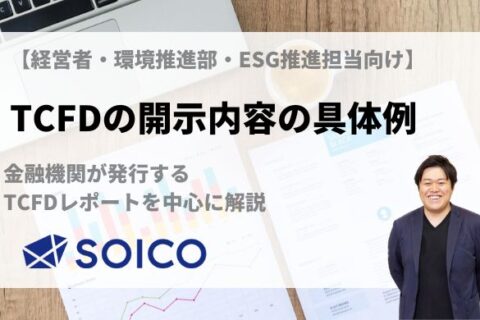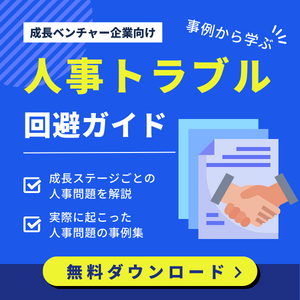COLUMN
コラム
OKRの導入事例10選|OKR導入の流れと実施に向けた注意点も合わせて解説
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)



『資金調達の手引き』
調達ノウハウを徹底解説
資金調達を進めたい経営者の方の
よくある疑問を解決します!
企業が従業員やチームの目標を管理して、全社的な目標を達成するための管理方法として、近年メジャーになっている方法がOKRです。
OKRは従業員やチームに達成可能な目標を与え、達成のための具体的な方法を示すことによって、チームも従業員個人も自然と目標を意識して仕事をするようになります。
OKR導入を検討している企業の方は、実際に導入している企業の具体例を詳しく見ていく中で、実際どのように企業にOKRを導入していくべきなのか、検討していくのがよいでしょう。
本記事では、OKRを導入している企業の具体例を徹底解説していきます。
改めて評価制度について学び直してからOKRを導入している企業の詳細を理解したい方は、以下の記事で詳しく解説しておりますのでこちらをご覧ください。
⇒評価制度とは?評価制度の目的・種類・制度の導入時に考えるべきポイントを解説
⇒人事評価とは?人事評価の目的・導入方法・注意点について解説
⇒人事評価シートの記載方法|人事評価シートの目的と職種別評価項目を徹底解説
⇒人事評価制度の作り方|評価を作る際の注意点や成功例についても解説
⇒人事評価の際の目標設定とは?目標設定のメリット・SMARTの法則を解説
⇒人事評価コンサルタント|メリット・デメリット・選ぶ際のポイントについて解説
⇒人事評価面談|面談の目的・進め方・ポイントについて解説
⇒人事評価制度のメリット・デメリット|デメリットの解決策・人事評価制度の失敗例についても解説
⇒人事評価の成功事例10選!人事評価項目の種類・人事評価制度の成功事例を幅広くご紹介!
目次
OKRとは
OKRとは企業がチームや従業員個人の目標を設定し、その進捗を管理することで、企業の生産性向上と従業員のモチベーション向上を図るものです。
OKRにはO(Objectives)とKR(Key Results)の2つの意味があります。
まずはOKRの具体的な意味について詳しく解説していきます。
OKRについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒OKR(目標と主要な成果)とは?目標の設定方法・運用の際のポイントを丁寧に解説
⇒OKRシートおすすめテンプレート5選|メリットと記入例・導入時の注意点も解説
⇒OKRを活用した人事評価のポイント|OKR評価を運用するコツも解説
⇒Google社におけるOKRの運用|Google流のOKR運用のポイントを丁寧に解説!
⇒OKRとKPIの違い|項目ごとの違い・制度の活用例・失敗例についても解説
O(Objectives)の意味
O(Objectives)とは、意義やゴールを示す定性的な目標のことを示します。
例えば、「売上10%アップ」など、企業が達成したい目標を最初に策定します。
そして、その目標達成に必要な目標をチームごとに設定し、チームの目標をさらに個人単位へ設定していきます。
売上10%アップの目標達成のために、商品開発チームは「売上向上のための新商品を3つ開発」という目標を立て、チーム内の従業員の1人は「新商品のうちの1つを半年以内に開発する」など、会社の目標をチームに、チームの目標を従業員個人にというように、定性的な目標を細かく立てていきます。
KR(Key Results)の意味
KR(Key Results)とは、目標達成のための定量的・客観的な成果のことです。
目標を達成するための具体的な成果指標と言い換えることもできます。
例えば、「新商品開発」という目標達成のため、「3ヶ月以内に競合他社の売れ筋商品に対する改善点や不満点のアンケートを1,000件取る」「商品案を10個以上提出する」などの目標を達成するために必要な具体的な行動指針を提示しなければなりません。
OKRはあくまでも会社やチームの生産性向上を図るための方法ですので、KR(Key Results)では達成可能な成果指標を設定することが重要です。
このようにOKRでは、まず目標を設定し、次にその目標を達成するための具体的な成果指標を設定、さらにその目標に対する進捗を確認できるようにすることによって、従業員個人やチームの目標達成を促すことができるものです。
設定する目標はあくまでも多少の努力で達成可能なものとなっているので、従業員個人のモチベーションを向上させる効果も期待できます。
OKRを設定する手順
OKRを設定する際には次のような手順で行います。
1.企業の目標(O)を設定する
2.目標達成のための企業の定量的な成果(KR)を設定する
3.部門やチーム・個人ごとのOKRを決める
4.定期的にOKRをレビューする
まずは企業全体として達成したい目標をいくつか設定します。
その後、目標達成のためにやるべき成果を設定し、その実現のための目標をチーム単位・個人単位に設定し、それぞれの定性的な成果であるKRを設定していきます。
これによって、従業員は自分の目標がどのようにチームに影響し、その目標達成のために具体的に何をすべきなのかを明確に把握できるようになり、これによってモチベーションが向上し、さらには会社全体の生産性が向上していくことが期待されます。
また、OKRは定期的に目標に対する進捗を本人や上司が確認して、その進捗に対するフィードバックを行うことが重要です。
定期的に進捗等を確認することによって修正すべき点などがあれば早期に解決することが重要です。目標を設定して放置するのではなく、必ず定期的に目標に対する進捗を確認するようにしましょう。
OKR導入の注意点
OKRを導入する際にはいくつか注意点があります。
・導入時や導入後の手間を確認する
・定着に時間がかかることを認識する
・達成度ではなくプロセスを評価する
・長期間実施する場合は短期的なゴールを設定する
・組織の流動性が高い企業では定着が難しい
何も考えずOKRを導入すると本業の妨げになったり、目標達成から逆に遠ざかってしまう可能性もあるので注意点についてもしっかりと認識しておく必要があります。
OKR導入の5つの注意点について詳しく見ていきましょう。
導入時や導入後の手間を確認する
OKRを導入する際には、それなりに手間がかかります。
また、導入した後もフィードバックや翌期の目標設定などのために手間や時間がかかります。
大きな企業の場合には、OKRを設定すべきチームや従業員の数も膨大なので、導入するだけでも相当な事務的なコストになります。OKRを導入する際には、導入のための事務的コストをかけることができるのか、導入しても本当に運用できるのかという点を必ず確認するようにしてください。
定着に時間がかかることを認識する
OKRを会社に導入してもすぐに定着するわけではありません。定着するまでには一定の時間がかかります。
従業員やチームが目標と成果指標を意識して仕事に取り組むようになるまでには1年程かかることを認識し、初年度は目標達成のための準備期間と認識して、焦って進めないということも重要です。
達成度ではなくプロセスを評価する
OKRは人事評価のためではなく、全社的な目標を達成させるための手段です。
そのため、目標に対する達成度がどの程度だったかではなく、プロセスを評価することが重要です。
プロセスを評価されることによって従業員はモチベーションが向上しますし、より成果に繋がりやすいプロセスを探すための方法を従業員自ら探すようになります。
すると、さらに全社的な生産性向上が期待できるでしょう。
長期間実施する場合は短期的なゴールを設定する
目標達成までの期間が1年以上の長期になる場合には、短期的なゴールを設定することも重要です。
目標の終了期間が長くなればなるほど、途中の行動が緩んでしまい、日々の生産性が落ちやすくなります。
1年で20%の売上向上という目標の場合には、「3ヶ月で5%の売上向上」など、長期の目標をできる限り短期に落とし込んで設定するようにしてください。
短期的な目標達成が、長期の目標達成につながるようなOKRとすることを意識しましょう。
組織の流動性が高い企業では定着が難しい
OKRでは従業員の出入りや、部署間の移動や、チーム再編が早い企業では定着させることは難しいのが実状です。
「会社→チーム→個人」へと目標を設定し、成果指標を策定するのがOKRです。
この際にはチームや個人の長所や得意分野をしっかりと把握して適切な目標や成果指標を策定する必要がありますが、流動性が激しい会社では適切な設定ができません。
ある程度人や組織が固定化されている会社ではOKRは目標管理の有効な方法ですが、流動性が高い企業においてはそもそも不向きであるという点もしっかりと認識しましょう。
OKRを実施している企業の10の事例
実際にOKRを導入して目標管理をしている会社として有名なのは次の10社です。
・株式会社メルカリ
・Chatwork株式会社
・株式会社ココナラ
・インテル株式会社
・Sansan株式会社
・freee株式会社
・大日本印刷株式会社
・株式会社日本ユニスト
・株式会社フィードフォース
・GMOペパボ株式会社
アメリカではGAFA(Google・Amazon・Facebook(現:Meta)・Apple)が導入していることでも有名ですが、日本でも多くの大手企業がOKRを導入しています。
実際にOKRを導入している企業が具体的にどのような運用をしているのか、詳しく見ていきましょう。
株式会社メルカリ
株式会社メルカリは、会社が大きくなるにつれ、企業の目標と個人の目標にズレが生じたことに問題意識を持ちOKRを導入しました。
OKRを導入したことによって、会社と個人の目標のズレが解消し、全社的に会社の目標達成に向かうことができる体制づくりができるようになりました。
Chatwork株式会社
Chatwork株式会社では、「OKRに対してどの程度チャレンジしたのか」が重視されています。
ChatworkのOKRは人事評価とは直結せず、あくまでも企業の生産性向上とイノベーション向上のために活用されています。
そのためOKRの評価が低くても人事評価では高い評価が与えられるケースもあります。人事評価とOKRを切り離しているという点がChatworkの特徴です。
株式会社ココナラ
株式会社ココナラは、以前からOKRを導入していましたが、当初定めた目標と最終的な目標がズレるという問題を抱えてしまいました。
この問題を解決するために、遅滞なくOKRの目標を再設定することを行っています。
また、業務の中にはOKRが適していないものもあるので、そのような日常的な業務に関してはOKRを適用していません。
このようにOKRを適宜ブラッシュアップしているのがココナラの大きな特徴です。
インテル株式会社
インテル株式会社は、OKRを最初に導入した企業として知られています。
それまではいくつも存在した活動内容をOKR導入によって1つの戦略に絞り、その戦略や目標を全社に共有することによって経営のV字回復を遂げました。
Sansan株式会社
Sansan株式会社は、クラウド名刺管理サービスを提供している会社です。
SansanのOKRは当初は個人単位のみでしたが、次第にチーム単位、会社単位でOKRを設定することによって会社全体のモチベーションや生産性が向上し、業績アップに繋がりました。
個人単位からOKR導入を始めた珍しい事例だと言えるでしょう。
freee株式会社
クラウド会計ソフトのfreee株式会社もOKRを導入しています。
創業初期からOKRを採用し、最初は数十人単位の小規模で運用していました。
創業4年目で従業員が50名から100名程度の規模となった時点で、人事制度を導入しましたがOKRと人事制度の紐づけは最小限として、OKRの「目標に対するアグレッシブなチャレンジ」という当初の意義はそのまま残しました。
さらに上場直近の本格的に会社が大きくなった段階から、挑戦重視のOKRと達成重視のOKRを使い分けるようになり、今はOKRによってプロセスと成果の両方が重視される仕組みとなっています。
大日本印刷株式会社
大日本印刷株式会社は、テレワークやダイバーシティー(多様性)に関連した人事制度を導入する一環としてOKRを導入しました。
特にテレワークの普及にともなって、テレワークの課題である「仕事の成果が見えない」という問題点を解決するためにOKRを導入しました。
OKRを導入すれば目標に対する成果が見える化するためです。OKR導入によってテレワークが普及しても、全社的な生産性の低下を防ぐことができる仕組みを確立することができました。
株式会社日本ユニスト
株式会社日本ユニストは、2011年に設立された総合不動産デベロッパーです。
日本ユニストも会社の目標と個人の目標がズレてしまうという問題を抱えていました。
そこでOKRを導入することによって、マネジメント力が強化され、会社の意思や目標が従業員に伝わりやすくすることに成功しました。
日本ユニストはOKR導入によってリモートワークも効率的かつ生産性を落とすことなく進められるようになりました。
株式会社フィードフォース
株式会社フィードフォースはデータフィード関連事業などを行う会社です。
1on1、OKR、ノーレイティングなど新しい評価制度や目標管理制度を次々に導入していることでも知られています。
フィードフォースは創業期からで1on1の導入、9ブロックによる評価制度、マトリックス型の組織の導入など組織づくりのために行っています。
新しい取り組みによってよりよい労働環境や生産性の向上などを次々に実践しています。
GMOペパボ株式会社
GMOペパボ株式会社は、2021年1月から全社でOKRを導入しています。
同社は新しく導入した人事制度において「個人の目標設定は任意」と決め、それに伴い個人の目標を管理する仕組みが必要になったことからOKRを人事評価と切り離して導入することになりました。
その結果、個人の成果がどうチームに貢献してるかが可視化され、メンバーのモチベーション向上に繋がり、人事評価で個人の目標を設定しないことの問題点を見事にクリアすることができることがわかりました。
まとめ
OKRとはまずは目標を設定し、目標達成のための成果指標を定量的に明示することです。
「企業→チーム→個人」という順番で目標や成果指標を設定するのが基本ですので、チームや個人の仕事の成果がどのように会社に寄与するのかを明確に把握できるため、従業員のモチベーション向上や生産性向上に寄与するのが大きな特徴です。
会社の目標と個人の目標が一致しないことはよくありますが、OKRを導入することによって会社と従業員を同じ方向に合わせることもできます。
OKRを導入することの注意点も意識しつつ、成功事例を参考に、自社にOKRを導入すべきかどうか慎重に検討するとよいでしょう。
人事制度について、こちらの記事もご参照ください。
⇒人事制度とは?人事制度の目的・設計・歴史・新しい人事制度について徹底解説!
⇒人事制度と設計時の注意点|人事制度の種類と構築の流れについて解説
⇒人事考課制度の作り方|会社と社員へ与える影響と運用の注意点を解説
⇒人事制度設計コンサルティングとは?選び方・費用相場・おすすめ企業も紹介
⇒等級制度とは?3種類の等級制度と作成方法・導入事例について解説
⇒評価制度とは?評価制度の目的・種類・制度の導入時に考えるべきポイントを解説
⇒報酬制度とは?役割・種類・制度設計の手順・導入時の注意点・事例について詳しく解説
新しい人事制度については次の記事もご参照ください。
⇒【2023年最新】トレンドの人事制度|最新人事制度9選を徹底解説
⇒MBO(目標管理制度)とは?具体例と作成時のポイント・OKRとの違いについて解説
⇒OKR(目標と主要な成果)とは?目標の設定方法・運用の際のポイントを丁寧に解説
⇒360度評価とは?評価制度の特徴・メリット・デメリット・導入の際のポイントなどを解説
⇒バリュー評価とは?評価制度の仕組みや特徴・メリットや注意点・導入事例まで解説
⇒ミッショングレード制とは?他の制度との関係・制度の導入に必要な役割定義書の作成方法まで詳しく解説
⇒コンピテンシー評価とは | メリット・デメリットや導入時の注意点をご紹介!
⇒ノーレイティングとは?メリット・デメリット・評価制度を成功させるポイントを解説
⇒ピアボーナスとは?導入のメリットやデメリット、具体的なツールを徹底解説!
スタートアップ・ベンチャーの経営をされている方にとって、事業に取り組みつつ資金調達や資本政策、IPO準備も進めることは困難ではないでしょうか。
財務戦略の策定から実行まで担えるような人材をを採用したくても、実績・経験がある人を見つけるのには非常に苦労するといったこともあるでしょう。
このような問題を解決するために、SOICOでは「シェアリングCFO®︎」というCFOプロ人材と企業のマッチングサービスを提供しています。
シェアリングCFO®︎では、経験豊富なCFOのプロ人材に週1日から必要な分だけ業務を依頼することが可能です。
例えば、ベンチャー企業にて資金調達の経験を持つCFOに、スポットで業務を委託することもできます。
専門的で対応工数のかかるファイナンス業務はプロの人材に任せることで、経営者の方が事業の成長に集中できるようになります。
「シェアリングCFO®︎」について無料相談を実施しているので、ご興味をお持ちの方はぜひ下のカレンダーから相談会の予約をしてみてくださいね!
この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。