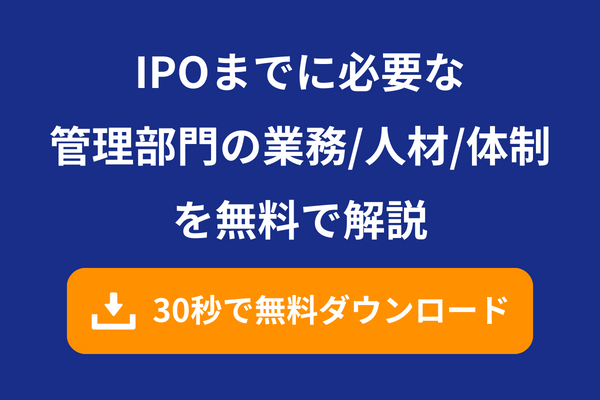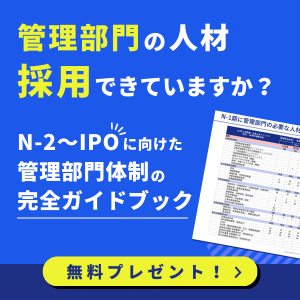COLUMN
コラム
IPOの費用は?準備時・上場時・上場後の時期別に詳しく解説!
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)
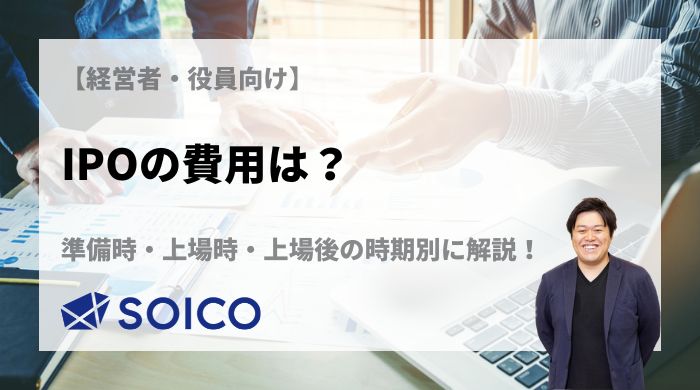

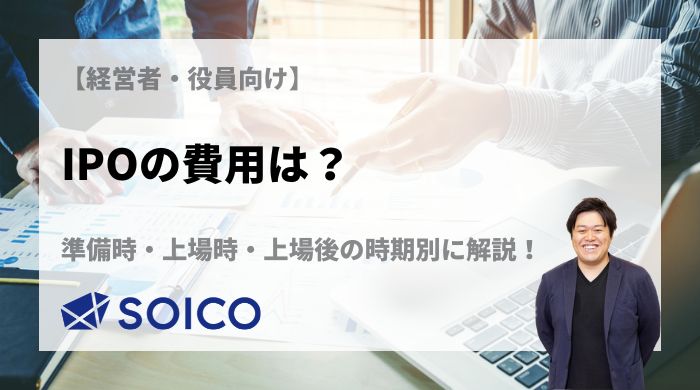
『資金調達の手引き』
調達ノウハウを徹底解説
資金調達を進めたい経営者の方の
よくある疑問を解決します!
会社を上場させるためには、銀行や証券会社だけでなく公認会計士・税理士・弁護士といった専門職および監査法人、IPOに特化したコンサルティング会社といった様々な事業者の協力が欠かせません。
したがって、IPOを行う企業の規模や依頼する内容等によって発生する費用も変わるため、正確な数値を述べることは難しいものがあります。IPOを行う際にかかる費用の目安として、参考にしていただければと思います。
実際にIPOの準備を行う際には、自社に必要なサポートは何かということを精査し、外部からのサポート不要なものは自社内で行うことで、費用コストを減らすことも考えましょう。
そのためにはIPOの準備の流れを知ることも大切になります。
本記事ではIPOを行う際にかかる費用を、IPO準備期間、IPO申請時、IPOを行ったあとの3つの段階別に分けて詳しく解説をしていきます。
目次
IPO準備期間にかかる費用

IPOの準備期間にかかる年間の費用は最低でも5000万円ほどとなっています。その内訳は、
・監査法人への費用
・主幹事証券会社への報酬
・証券印刷会社への費用
・株式事務代行機関の費用
・IPOコンサルティング会社への費用
・内部統制に係る費用(J-SOXコンサルティング)
・弁護士の費用
・税理士・社労士・司法書士の費用
となっています。
IPOの準備期間については、こちらの記事もご参照ください。
⇒IPOの準備スケジュール|直前前々期から申請期まで解説
監査法人への費用
監査法人は、株式上場の審査において会計監査を行い、最新の会計基準のもと上場を検討している企業が適切に会計処理を行っているかについて指導およびアドバイスを行う役割を果たします。とくに、上場申請の直近の2期の決算の監査証明が必要なので、それより前の期に監査の依頼をする企業が多い傾向があります。
監査の作業内容ごとに工数を見積もり計算されますが、会社の状況により作業内容は変わるため、それに伴って報酬が決まります。報酬を決める要素は、財務数値(売上高、各種利益、総資産等)、業種、連結会社の有無、子会社数、拠点数、人員数などです。
監査法人にかかる費用の相場は1事業年度あたり800〜2000万円ほどです。
監査法人については、こちらの記事もご参照ください。
⇒IPOにおける監査法人の役割とは?監査法人を選ぶポイントも解説!
主幹事証券会社への報酬
一般的に、株式上場を行う際は複数社の証券会社によって発行する株式を引き受け、販売してもらいます。その中で、株式を引き受ける中心となる証券会社を主幹事証券会社といいます。主幹事証券会社はIPO全体のスケジュール管理や、公開価格の決定などの中心的な役割を担い、上場までの手続きの様々な場面で重要な役割を果たします。
上場申請をする企業は、主幹事となる証券会社の推薦を受けることが必要です。また、企業は監査法人と同じ上場申請の直前2期前の時期に依頼する企業が多い傾向があります。したがって、証券取引所の上場審査は、株式上場を希望する企業が適格であるかについて主幹事となる証券会社が十分に知っていることを前提に行われます。
主幹事証券会社にかかる費用は年間約500万円〜2000万円程度が相場です。
主幹事証券会社については、こちらの記事もご参照ください。
⇒主幹事証券会社とは?役割・選び方・変更について解説
⇒IPOにおける主幹事証券会社の選び方|主幹事選択の事例と証券会社について解説
⇒IPOにおける主幹事証券会社の役割|引受審査や選び方についても解説
証券印刷会社への費用
申請資料は専門的な内容であり、量も非常に多くなるため、機密保持という観点からも専門の印刷会社へ依頼するのが一般的です。また、会社法や証券取引法、証券取引所の規定に則り、企業情報の公開を行わなければならないため、これらの規定を熟知している証券印刷会社に書類作成のサポートを依頼することになります。
証券印刷会社にかかる費用は、年間500万円ほどになります。
IPOコンサルティング会社への費用
IPOを行うには経営管理体制を整備し適切に運用すること、会計監査を受けること、証券会社の引き受け審査を受ける、証券取引所の審査を受ける、また諸所の手続きのための書類作成等の事務作業などやらなければならないことが多くあります。そのため、IPOコンサルティング会社を利用することが一般的です。
IPOコンサルティング会社には、大きく分けると
・審査のための書類作成などの審査に関わる業務を得意とする「証券会社系コンサルタント」
・内部統制や決済開示体制の整備を得意とする「会計士系コンサルタント」
・IPOを行う企業側の忙しさなど現場のこと熟知している「ベンチャー・スタートアップ系コンサルタント」
の3つの種類の会社があります。
会社の規模や、会社が依頼したい内容によって費用は変わってきますが、年間約500万円〜1500万円ほどが相場となっています。
IPOコンサルティングについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒IPOコンサルティングの種類や業務とは?必要なコストや選ぶ際のポイントも徹底解説!
内部統制に係る費用(J-SOXコンサルティング)
IPOを行うためには、内部統制構築・評価をすることが求められます。内部統制の構築のために、J-SOXコンサルティングという内部統制構築の専門家に依頼する場合があります。J-SOXコンサルティングは全社統制や業務処理統制、決算統制、IT統制などの統制システムを見直し、調査・計画・整備構築・教育運用・評価・是正という流れで内部統制の構築をしていきます。
J-SOXコンサルティングを利用する場合、会社にもよりますが年間約500〜1000万円ほどになります。
内部統制・J-SOXについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒内部統制とは?会社法・金融商品取引法での定義や方針を徹底解説!
⇒IPOに内部統制が必要な理由とは?構築する目的・要素も解説!
⇒J-SOXとは?内部統制の目的とJ-SOXの具体的な進め方と役割について解説
⇒J-SOXの3点セットとは?作成目的や手順をサンプルを交えて解説
⇒J-SOX対応における内部監査部門が担う役割とは?J-SOXの3点についても解説
弁護士の費用
IPOでは会社法・金融商品取引法などの法律を気にすることが必要です。そのため、弁護士と顧問契約を結びます。顧問契約を結ぶことで、有効な書類作成のためのサポートや上記の法律に反していないか等をチェックすることができるようになります。軽微な法律相談に関しては顧問料のみで対応してくれることがありますので確認してみてください。
契約する内容にもよりますが、弁護士の費用は年間数十万円〜500万円ほどになります。
IPOに関わる法務については、こちらの記事をご参照ください。
⇒IPO準備に法務は必要?上場審査での法務の役割・業務を解説!
税理士・社労士・司法書士の費用
その他に、複雑な税務処理に対応できる税理士や、労働・社会保険の問題の専門家である社労士、登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家である司法書士を利用することもあります。
上場時にかかる費用

上場審査料
上場申請時には上場審査料を支払う必要があります。以前は、東証一部・東証二部・マザーズ・JASDAQといった市場がありましたが、2022年4月4日以降は以下のような市場区分に再編されました。
| 市場区分 | 上場審査料 |
|---|---|
| プライム市場 | 400万円 |
| スタンダード市場 | 300万円 |
| グロース市場 | 200万円 |
参考:https://www.jpx.co.jp/equities/listing/fees/01.html
新規上場料
上場の際には新規上場料が発生します。上場審査料と同じく、以前にあった市場区分は廃止されて、2022年4月4日以降は以下の区分に再編されました。
| 市場区分 | 新規上場料 |
|---|---|
| プライム市場 | 1500万円 |
| スタンダード市場 | 800万円 |
| グロース市場 | 100万円 |
参考:https://www.jpx.co.jp/equities/listing/fees/01.html
株式の公募または売出に係る費用
上場した株式の公募または売出しについて、その数に応じて以下のような費用を払わなければいけません。
・上場申請に係る株券等の公募
公募株式数 × 公募価格 × 1万分の9
・上場申請に係る株券等の売出し
売出株式数 × 売出価格 × 1万分の1
※100円未満の金額は切り捨て
※グロース市場のみ公募または売出に係る費用の上限は1900万円
登録免許税
登録免許税は会社や不動産の登記・登録の際にかかる税のことです。とくに、株式会社設立の登記の場合は、資本組入額に税率の0.7%をかけることで税額を計算することができます。資本組入とは、会社の損失に備えた資本準備金の一部を資本金に組み入れることをいいます。
資本組入額×1000分の7
※資本金が15万円未満のときは1件につき15万円
詳細については、国税庁のサイトを参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
証券会社の引受手数料
IPOの際に株式の公募を行う場合には、一般的には証券会社に発行する株式を買い取ってもらいます。このことを株式の引受といいますが、その際証券会社に対して手数料を支払うことになります。
手数料の目安としては、約5%〜9%ほどになります。
公募価格と発行価格に差をつけ、その差額を引き受け手数料とする、スプレッド方式を採用している証券会社の場合は、会社が支払う手数料は発生しません。
上場後にかかる費用

上場維持費(年間上場料)
上場会社は、年間上場料を支払わなければなりません。金額は以下の表の料金となります。
| 上場時価総額 | プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 |
|---|---|---|---|
| 50億円以下の場合 | 96万円 | 72万円 | 48万円 |
| 50億円より大きく250億円以下の場合 | 168万円 | 144万円 | 120万円 |
| 250億円より大きく500億円以下の場合 | 240万円 | 216万円 | 192万円 |
| 500億円より大きく2500億円以下の場合 | 312万円 | 288万円 | 264万円 |
| 2500億円より大きく5000億円以下の場合 | 384万円 | 360万円 | 336万円 |
| 5000億円より大きい場合 | 456万円 | 432万円 | 408万円 |
※消費税額及び地方消費税額別
参照:https://www.jpx.co.jp/equities/listing/fees/02.html
また新規上場をした年間上場料は上場をした月によって異なります。詳細は、以下のJPXのサイトをご覧ください。
https://www.jpx.co.jp/equities/listing/fees/02.html
新株発行等の費用
上場後に株式の売出しを行う場合にも証券取引所に対する支払いが発生します。
上場株券等を発行又は処分する場合: 1株当たりの発行価格 × 発行又は処分する株券等 × 1万分の1
新株予約権の目的となる株式が上場株式である新たな新株予約権を発行する場合:(新株予約権の発行価格×新株予約権の総数+新株予約権の行使に係る払込金額 × 新株予約権の目的となる株式の数)× 1万分の1
上場株券等の売出しの場合: 売出株式数 × 売出価格 × 1万分の1
新株予約権については、こちらの記事もご参照ください。
⇒【新株予約権とは?】種類・メリット・デメリットについて解説
新株上場の料金
上場会社が新たに発行する株券等を上場する際には、以下の料金が必要となります。
新株の上場に係る料金: 1株当たりの発行価格 × 発行又は処分する株券等の数 × 1万分の8
合併にかかる料金
上場会社が吸収合併等(吸収合併、吸収分割、株式交換又は株式交付)を行う場合に以下のような費用が発生します。
合併等に係る料金: (その合併等に際して発行する株券等の数 + 交付する自己株式の株券等の数) × 合併等の効力発生日の売買立会におけるその株式の最終価格 × 1万分の2
監査報酬
上場会社は金融商品取引法第193条の2第1項において、会社と特別の利害関係のない公認会計士又は監査法人の監査証明を受けなければならないと定められています。そのため、監査を公認会計士もしくは監査法人に依頼する必要があるため、そのための監査費用が発生します。
会社の規模にもよりますが、年間約1000万〜数千万円ほどの費用がかかります。
株式事務代行手数料
上場会社は会社法で名義書換代理人として株式事務代行機関の設置が義務付けられています。そのため、各証券取引所の指定する信託銀行、または証券代行会社と契約を結ばなければなりません。
株式事務代行機関は、株式関係の事務をスムーズに行うことを目的とした組織であり、株主名簿作成事務等の受託、株主総会における議決権や株式配当等の株主に付与されるさまざまな権利の処理を行います。
ベンチャー企業であれば、年間約400万円程度であり、会社の規模が大きくなるほど、年間約1000万円から8000万円など費用は大きくなります。
2022年9月1日時点で東京証券取引所が承認をしている株式事務代行機関は
・信託銀行
・東京証券代行株式会社
・日本証券代行株式会社株式会社
・株式会社アイ・アールジャパン
となっています。(有価証券上場規程施行規則第212条第7項)
株主総会の運営費用
株式代行事務に加えて、株主総会自体の運営費用も上場後の費用として考えられます。決算期末から3ヶ月以内に株主総会を開催して、株主を招待しなければなりません。また上場後は、さまざまな投資家が株主であることが想定されるので、ある程度の大きさのある会議室などを抑える必要があります。
来場する株主の人数にもよりますが、株主総会の会場費用や弁当代、懇親会の費用、お土産代などが費用としてかかります。
リーガルチェックにかかる弁護士費用
株式上場をする企業から金融庁や証券取引所に対して提出する開示書類は、金融商品取引法だけでなく上場規則などを理解している実務に強い弁護士によるリーガルチェックが必要となってきます。
一般的に顧問弁護士として契約をする場合は、月額3〜5万円が顧問料の相場になります。ただし、事業に関わる簡単な法律相談までの範囲であることが多く、株式上場に向けた専門性の高い内容について依頼することになると着手金などが別に必要となってきます。
株式上場に関するリーガルチェックについては、弁護士事務所によって決まった報酬体系があるわけではありません。金融商品取引法関連が得意であり、かつ、顧問料の範囲でリーガルチェックに対応してもらえる事務所もあると言われています。リーガルチェックについては
・月10件程度 : 約3万円〜約10万円
・月10件から20件程度: 約10万円〜約20万円
が報酬の相場であるとも言われています。
TDnetサービス料
TDnet(適時開示情報伝達システム)は、
①東証への開示資料の提出
②東証への事前説明(開示内容の説明)
③「適時開示情報閲覧サービス」への掲載
④「東証上場会社情報サービス」への掲載
⑤報道機関への情報配信
⑥ファイリング(開示資料のデータベース化)
を電子化するサービスです。
上場会社は規則により、TDnetを利用することが義務付けられています。
TDnet利用料金は年間約44万円になります。(年間12万円から値上がりしています)
まとめ
IPOにかかる費用について解説をしてきました。IPOは、一括で1つの機関に支払いをするのではなく証券会社や監査法人、証券代行機関、弁護士、税理士、IPOコンサルティング会社、印刷会社など多くの関係者への金銭の動きが発生します。
必ずしも必要のないものもあるため、会社に必要なサポートは何かということを精査し、会社に必要なサービスを選択することで、できる限り費用を抑えることも重要です。
現在スタートアップ・ベンチャー企業を経営していて上場を目指されている方にとって参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
また、管理部門体制の構築をしたり、CFO人材の採用を進めたり、資金調達を加速させたりするには、プロの専門家に相談するのが一番です。
そこでSOICOでは、CFO中心とした管理部門組織の構築や、ファイナンスに長けたプロによる、個別の無料相談会を実施しております。
・CFOやバックオフィスの部長クラスが採用できている会社は、給与/役員報酬、株式報酬、採用手法は具体的にどうやっているか?
・今の自社の経営状態を踏まえた上で、資金調達を失敗しないために、どういったポイントを意識して進めるべきか?
そんなお悩みを抱える経営者の方に、要望をしっかりヒアリングさせていただき、
適切な情報をお伝えさせていただきます。
ぜひ下のカレンダーから相談会の予約をしてみてくださいね!
この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。