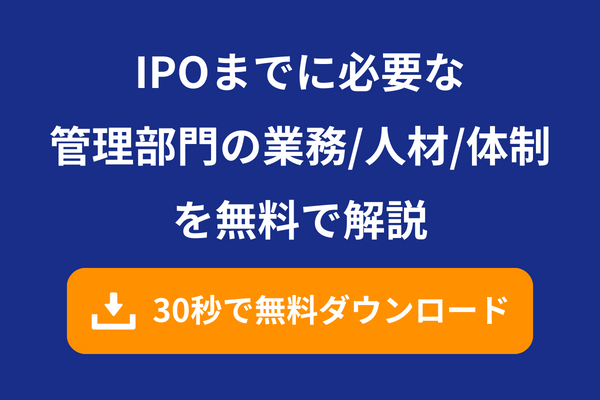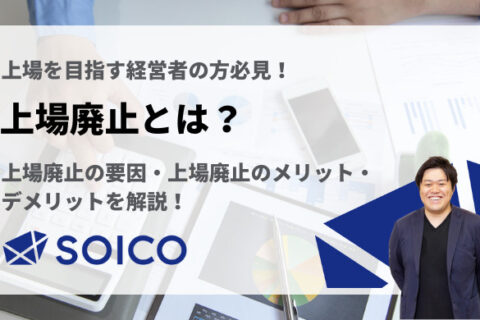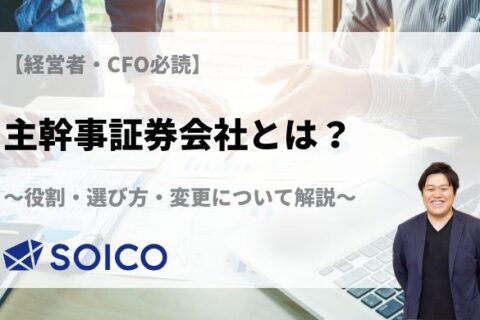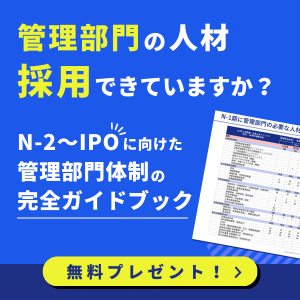COLUMN
コラム
【経営者必読】赤字上場は可能?赤字でIPOした企業の特徴・理由・事例を紹介
執筆者:茅原淳一(Junichi Kayahara)
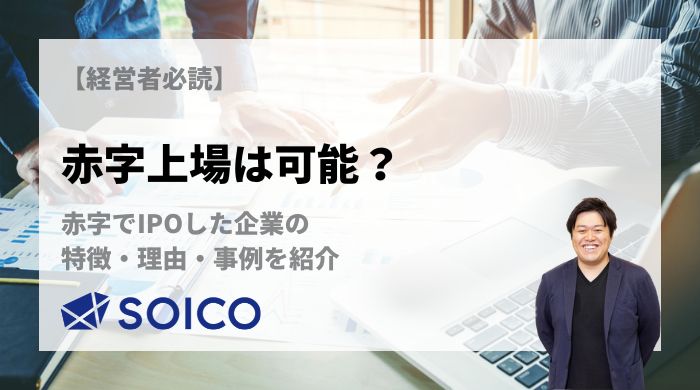

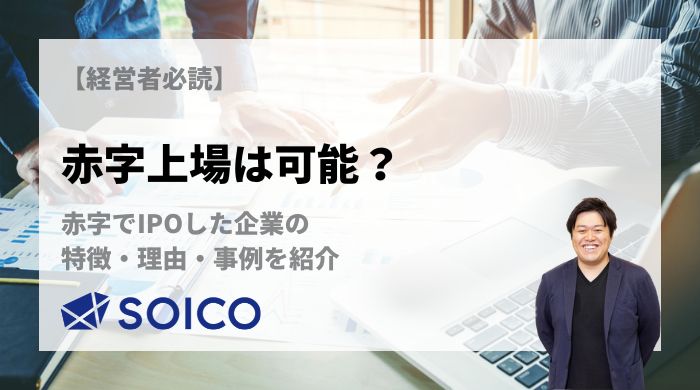
『資金調達の手引き』
調達ノウハウを徹底解説
資金調達を進めたい経営者の方の
よくある疑問を解決します!
事業の拡大、組織力の強化を目的に上場を検討している企業の経営者の中には、赤字のまま上場できるのか悩んでいる方もいると思います。
赤字上場している有名な企業の存在は知っているけれども、赤字のまま上場する条件までは知らないという話を耳にすることもあります。
そこで、本記事では赤字で上場する企業について、その特徴やメリット、事例について解説していきます。
目次
赤字上場とは

赤字上場とは、企業の直近の決算が「赤字」の状態でも上場審査を通過して、企業が上場することをいいます。
ここで、決算が赤字の企業全てが上場できるわけではないという点に注意しなければなりません。上場できる市場が限られており、また、その市場の上場審査に通過するには企業の「高い成長性」への期待が重要視されていると言われています。
上場基準・上場審査については、次の記事もご参照ください。
⇒IPOの準備スケジュール|直前前々期から申請期まで解説
⇒上場審査とは?審査基準・審査の流れ・審査通過のポイントを徹底解説!
赤字上場が可能な市場
2022年4月以前、市場が再編されるまでは赤字上場できる市場は東証マザーズ市場だけでした。市場再編された後はグロース市場だけが赤字上場できる市場になります。
市場再編以前に東証マザーズ市場だけでしか赤字上場できなかった理由として、以下の点が挙げられます。
・高い成長性への期待
・高リスク企業向けの市場
東証マザーズ市場の後継にあたるグロース市場が似た役割を担っているので、現在はグロース市場で赤字上場をすることができます。
グロース市場については、こちらの記事もご参照ください。
⇒グロース市場とは?市場区分の再編による変化を徹底解説!
上場のための基準
上場基準には、「形式基準」と「実質基準」という2つの基準があります。
上場基準が設けられている理由として、株式の上場に対して厳しい条件がないと、上場後すぐに倒産してしまったり、資金調達を目的に企業の業績や財務情報を改ざんしたり、株式市場が混乱してしまう恐れがあることが考えられます。
上場市場にある企業の入れ替わりが多かったり、公開されている有価証券報告書に嘘があると投資家は安心して株取引をすることができなくなります。
このような事態を招かないようにするために、証券取引所などの外部組織による厳しい審査を行っています。
上場基準については、こちらの記事もご参照ください。
⇒上場のために必要な売上基準とは?IPOのための業績について解説
以下にて、各基準の概要について解説していきます。
形式基準
軽視基準とは、上場申請する上で最低限クリアするべき基準を指し、この基準をクリアできなければ上場申請を通過することは不可能です。
市場区分別に求められる基準は異なりますので、以下にて各市場ごとの要件を可視化しました。
| 項目 | プライム市場 | スタンダード市場 | グロース市場 |
|---|---|---|---|
| 株主数 | 800人以上 | 400人以上 | 150人以上 |
| 流通株式 | a,流通株式数20,000単位以上 b,流通株式時価総額100億円以上 c,流通株式比率35% |
a,流通株式数2,000単位以上 b,流通株式時価総額10億円以上 c,流通株式比率25% |
a,流通株式数1,000単位以上 b,流通株式時価総額5億円以上 c,流通株式比率25% |
| 公募の実施 | – | – | 500単位以上の新規上場申請にかかる株券等の公募を行うこと |
| 事業 継続年数 |
3か年以前から取締役会を設置していること | 3か年以前から取締役会を設置していること | 1か年以前から取締役会を設置していること |
| 財政状況 |
(i)純資産要件 |
・連結純資産の額が正であること ・直近1年間の利益額が1億円以上あること |
– |
参考:日本取引所グループ>株式・ETF・REIT等>上場制度(内国株)>上場審査基準>上場審査基準概要(スタンダード市場)
実質基準
実質基準とは、形式基準のように明確に数字で定量的に示されているものではありませんが、上場企業に相応しいかの適格性を判断するための基準です。
赤字企業が上場を目指すグロース市場の場合、主な実質基準には以下のような内容が挙げられます。
企業内容・リスク情報等の開示の適切性
企業内容やリスク情報などの開示を適切に行うことができる状況にあることが求められます。
具体的には、会社情報を適時かつ適切に開示することができる状況にあること、法令に則った書類が作成できていることなどが求められています。
企業経営の健全性
事業を公正かつ忠実に遂行していることが求められます。
特定の者に不当に利益を与え、享受していないかなどがこの基準の要諦であり、厳格に特定の範囲で利益の搾取が行われていないかを判断されます。
企業のコーポレートガバナンスおよび内部管理体制の有効性
役員の適正な職務の執行を確保するための体制が整備されているものの、適切に運用されておらず、単に親族が役員になっていたり、社外取締役がいなかったりするとコーポレートガバナンス(※)の有効性が実証されず、審査に影響する可能性があります。
※コーポレートガバナンスとは、企業は経営者のものではなく、株主のものであるという考えのもと、経営監視に努める仕組みを指します。
また上場審査では、内部統制(※)を行う体制や適正な会計処理基準の採用や会計組織の運営なども審査対象となります。
※内部統制とは、不正が起こらないように適正な業務を実行するための仕組みです。
内部統制・コーポレートガバナンスについては、こちらの記事もご参照ください。
⇒IPOに内部統制が必要な理由とは?構築する目的・要素も解説!
⇒コーポレートガバナンス(企業統治)とは?目的・強化方法・歴史的背景について解説!
事業計画の合理性
相応に合理的な事業計画を策定しており、当該事業計画を遂行するために必要な事業基盤を整備していること、または整備する合理的な見込みのあることが求められます。
赤字上場する企業に共通する特徴
赤字上場している企業に共通する特徴として、成長性が挙げられます。この成長性は企業自体の成長だけでなく市場の成長性も含まれます。それぞれ「成長性の外部要因」と「成長性の内部要因」に分けて説明していきます。
成長性の外部要因
成長性の外部要因として、以下のようなものがあります。
・技術革新の普及
・政府による法律の規制緩和や政策投資
・感染症の世界的な流行
それぞれ説明します。
技術革新の普及
技術革新の普及は、誰もがインターネットや携帯電話・スマートフォンの利用などをするようになったハード面やインターネット上で個人と個人がつながるようになったSNSや映像と音声でリアルタイムでコミュニケーションできるzoomのようなソフト面での技術の進化などがあります。これによって、企業の在り方・日々の業務のやり方および個人の行動やライフスタイルが変わることは事業の成長の外部要因になり得ます。
政府による法律の規制緩和や政策投資
都内でよく見かける「電動キックボード」は、今まさに規制緩和されつつあります。ヘルメットの着用が必須でなくなったり、運転免許証が不要になったことなどが道路交通法の改正によって緩和されました。
また、国家の政策として「スタートアップ企業の創出」の支援強化が2022年1月に発表されました。地方へのデジタル投資の強化やエネルギー・脱炭素など気候変動問題への対応など国の動きによって成長産業になることが期待されます。
感染症の世界的な流行
昨今、世界的に大きな影響を与えたコロナウィルスは、マスク需要の激増や食事のデリバリー、テレワークなど私たちの生活を大きく変えました。
食事のデリバリーによってウーバーの配達員が増えて食事の宅配の機会が増えたり、テレワークが定着化したことで長時間座るのに適したイスやビジネス用デスクとモニターの需要が増加したことなど関連する企業にとっては事業成長に繋がりました。
成長性の内部要因
成長性の内部要因として、以下のようなものがあります。
・企業のビジネスモデル
・競合優位性の高い製品・サービス
・強固な組織体制
以下にてそれぞれ説明します。
企業のビジネスモデル
その企業にしかないビジネスモデルは、成長性の内部要因になります。独自の仕入れ先や自社にしかないチャネル、顧客との関係性など赤字でも上場している企業はビジネスモデルの成長性などが強く評価されていると考えられます。
競合優位性の高い製品・サービス
近年、赤字上場している企業の中には、他社が真似できない質の高いサービスを「サブスクリプション形式」で提供しています。提供されるサービスに対して毎月定額の利用料をいただくので、SaaSなどのサービスは顧客が増加することで、収益性の高い売上が見込めます。
強固な組織体制
組織体制の強さも成長性の内部要因として考えられます。人手が足りずに顧客からの事業の満足度が下がったり、事業に対して人員過多でコストだけかかっている状況だと組織体制に成長性は期待できません。反対に、既存事業が安定している傍らで、新規事業に挑戦できる体制が整っていると企業の更なる成長が期待できます。
赤字上場のメリット

赤字上場には上場審査を通過しにくいというデメリットがありますが、赤字上場することにもメリットはがあります。赤字上場のメリットとして以下の点が挙げられます。
・認知度の向上と資金調達
・上場の成長率のまま黒字化
認知度の向上と資金調達
上場すると、一般投資家も株式を購入することができるので多くの人の企業名が知られることになります。外部にも有価証券報告書などで情報を公開することになるので、投資家の中には事業のビジネスモデルと現在の財務情報から成長性を感じて株式を購入してもらえる可能性があります。上場をきっかけに投資家から注目されることで、大きな資金調達の機会が得られます。
したがって、現在赤字であることを理由に上場を先延ばしにしてしまうと成長につながる資金調達の機会というメリットを逃してしまうかもしれません。
資金調達については、こちらの記事もご参照ください。
⇒資金調達の手段・方法には何がある?それぞれのメリット・デメリットも徹底解説!
⇒ベンチャー・スタートアップの資金調達方法とは?投資ラウンド別・調達事例を含めて徹底解説!
⇒返済不要な資金調達とは?メリットやデメリット、調達時の注意点を徹底解説!
⇒資金調達コンサルティングサービスとは?選び方や注意点まで徹底解説!
⇒IPOに向けた成功する資本政策|上場後の資金調達の仕組みも解説
上場の成長率のまま黒字化
上場をきっかけに企業の知名度が上がり、資金調達で得た事業資金を適切に投資することで上場時の成長率のままの黒字化が期待できます。既存の事業部門やバックオフィスの強化に投資したり、新規事業の開発や市場開拓、営業など企業の成長率の向上につながる投資など、現在赤字だとしても黒字に向けた事業の成長が見込めます。
赤字上場を果たした企業事例
ベースフード株式会社

完全栄養食「BASEFOOD」シリーズを販売するベースフード株式会社は、2022年11月グロース市場に新規上場します。直近の経常損失は4億6000万円の赤字になります。この赤字の大半を占めているのは、広告宣伝費になります。テレビCMを打ち出して、日本全国の一般消費者への認知度を広げていき、同時にコンビニでの販売に力を入れたことで、2022年2月には売上高55億4500万円まで成長しました。
ベースフードの高い成長性が認められたのは、自社で展開しているECサービスのサブスクリプション会員数だと推察されています。
ランサーズ株式会社

クラウドソーシングサービスを提供するランサーズ株式会社は、2019年12月東証マザーズへ上場しました。主力事業である「Lancers」は、プラットフォーム上で業務内容を依頼したい企業と業務を請け負う個人をマッチングするサービスになります。2020年3月期の営業損失2億1483万円、経常損失2億1806万円の赤字でしたが、上場を果たしています。
コロナウィルスの蔓延や社会的なテレワークの推進と在宅ワークの環境が整ってきたことを背景に、クラウドソーシングの需要が高まったことが、ランサーズの高い成長性と考えられ、赤字上場をしたと言われています。
Sansan株式会社

法人向けクラウド型名刺管理サービスを提供するSansan株式会社は、2019年6月東証マザーズへ上場しました。Sansanは、クラウド名刺管理サービス「Sansan」とクラウド名刺を基盤にした個人向けビジネスSNS「Eight」というサービスを展開しています。2018年5月期の売上高は73億1800万円、経常損失は30億2200万円もの赤字でした。この赤字の原因は、売上高を上回る販売管理費や広告宣伝費によるものになります。
サービス内容やビジネスモデルの競争優位性や情報データベースとしての価値、そして市場機会と成長ポテンシャルなど事業の成長性については高い評価を得ていました。これが、赤字のまま上場できた背景だと考えられています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
本記事では、赤字で上場する企業について、その特徴やメリット、事例について解説をしました。
現状が赤字決算である企業だとしても、グロース市場で上場することは可能です。赤字上場でも成長性が期待できる企業であれば、投資家からの知名度が高まり、十分な資金調達をし、企業の成長につながる部門・事業部への投資によって、黒字化が期待できます。
この成長性は、技術革新の普及や政府による規制緩和や投資強化のような外部環境や企業のビジネスモデルや競合優位性の高いサービスのような内部環境などに影響されるので、必ずしも全ての企業が赤字上場できるわけではありません。
本記事が上場を目指しているスタートアップ・ベンチャー企業の経営者の方の参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございます。
また、管理部門体制の構築をしたり、CFO人材の採用を進めたり、資金調達を加速させたりするには、プロの専門家に相談するのが一番です。
そこでSOICOでは、CFO中心とした管理部門組織の構築や、ファイナンスに長けたプロによる、個別の無料相談会を実施しております。
・CFOやバックオフィスの部長クラスが採用できている会社は、給与/役員報酬、株式報酬、採用手法は具体的にどうやっているか?
・今の自社の経営状態を踏まえた上で、資金調達を失敗しないために、どういったポイントを意識して進めるべきか?
そんなお悩みを抱える経営者の方に、要望をしっかりヒアリングさせていただき、
適切な情報をお伝えさせていただきます。
ぜひ下のカレンダーから相談会の予約をしてみてくださいね!
この記事を書いた人
共同創業者&代表取締役CEO 茅原 淳一(かやはら じゅんいち)

慶應義塾大学卒業後、新日本有限責任監査法人にて監査業務に従事。 その後クレディスイス証券株式会社を経て2012年KLab株式会社入社。 KLabでは海外子会社の取締役等を歴任。2016年上場会社として初の信託を活用したストックオプションプランを実施。 2015年医療系ベンチャーの取締役財務責任者に就任。 2018年よりSOICO株式会社の代表取締役CEOに就任。公認会計士。